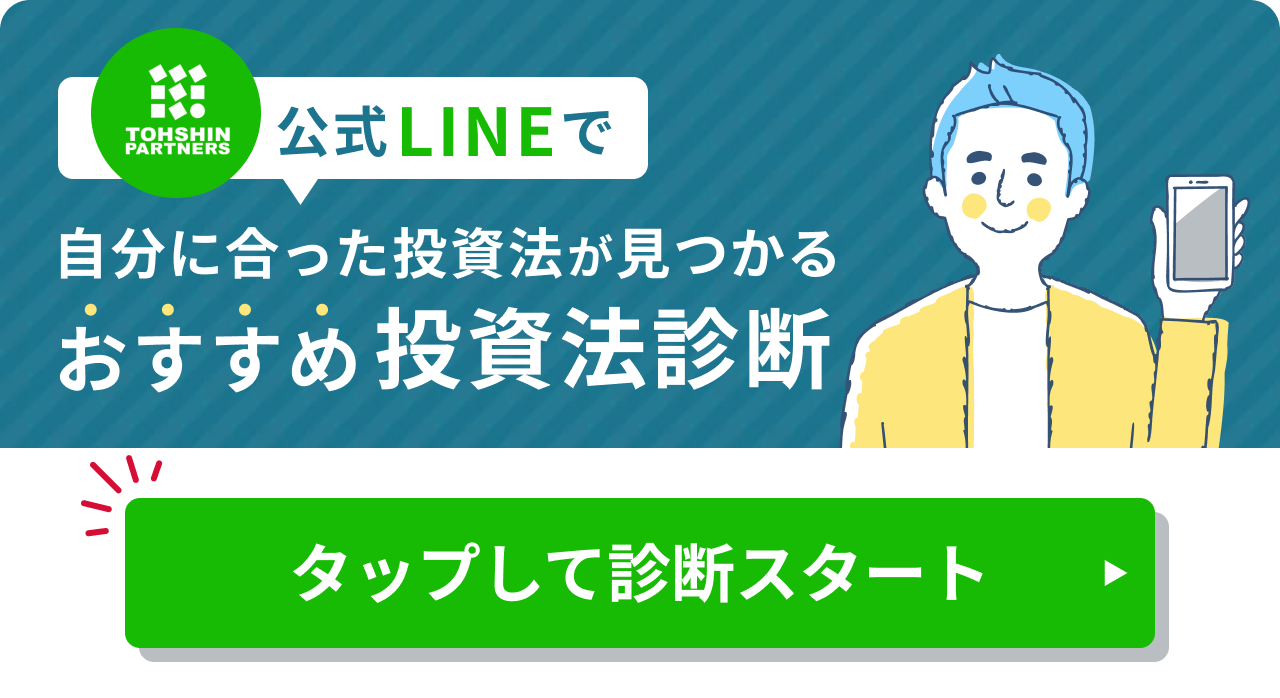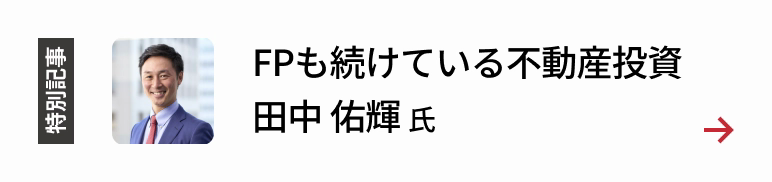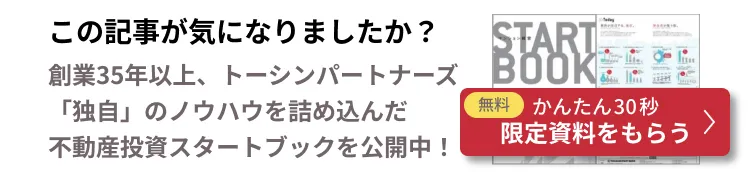- 不動産投資の基礎知識
表面利回りとは物件価格に対する年間家賃収入の割合|利回りの落とし穴と物件選定のポイント

不動産投資では投資物件を選ぶ際の指標として、利回りが用いられています。利回りには表面利回りのほか、想定利回りや実質利回りといった種類もあります。不動産投資会社から紹介される物件資料や、ポータルサイト上で見られる利回りの多くは「表面利回り」です。また、必ずしも高利回り物件が不動産投資の優良物件とは限りません。なぜなら、過度に高い利回りには理由があり、空室リスクや修繕費用などの隠れたリスクが潜んでいる可能性があるためです。
今回は表面利回りと想定利回りの違いを押さえたうえで、投資物件の選定の際には実質利回りを用いるべき理由や利回りにおいて気をつけるべき点、高利回り物件のチェックポイントなどを解説していきます。
表面利回りとは物件価格に対する年間家賃収入の割合

表面利回りとは、物件の購入価格に対して、1年間でどれくらいの家賃収入が得られるかを示す指標です。表面利回りの計算式には、マンションの購入時の諸費用や維持管理費などは含まれていません。そのため、表面利回りの計算式で算出された数値は、手元に残る収益を示すものではないという点に注意が必要です。
一般的に「利回り」と呼ばれ、投資物件の広告などで用いられているのは表面利回りです。
不動産の表面利回りの計算方法
表面利回りの計算方法は、以下のとおりです。
| ■表面利回りの計算式 表面利回り(%)=年間家賃収入÷物件購入価格×100 |
表面利回りの計算式を使って、2つの例を挙げて計算してみます。
| 物件1 | ⚫︎物件購入価格:3,000万円 ⚫︎年間想定家賃収入:150万円 |
| 物件2 | ⚫︎物件購入価格:5,000万円 ⚫︎年間想定家賃収入:200万円 |
物件1:150万円÷3,000万円×100=5%
物件2:200万円÷5,000万円×100=4%
表面利回りは、「物件1」は5%、「物件2」は4%のため、物件1の方が表面利回りが高く、表面的には多くの収益を得られると判断できます。
また、アパートやマンションなどは常に満室であるとは限らないことから、表面利回りは空室状況を加味した年間の家賃収入をもとに計算します。
想定利回りとの違いにも注意!
表面利回りと類似する指標として、想定利回りがあります。想定利回りは、満室時を想定した利回りという意味です。新築マンションはこれまでの賃貸実績がないことから、想定利回りで計算されるのが一般的です。
表面利回りが空室状況を加味して年間家賃収入を算出するのに対して、想定利回りは満室時を想定しているという違いがあります。マンションの購入時の諸費用や維持管理費などは含まれていないという点では、表面利回りと同様です。
中古マンションでも、不動産広告や投資物件のポータルサイトなどでは、想定利回りが用いられていることが多いため注意が必要です。
物件を選ぶ際は表面利回りよりも「実質利回り」を確認

表面利回りだけを参考にして、先ほどの例のように「物件1」の方が収益性が高いという判断をして、投資物件を選ぶのはリスクを伴います。
表面利回りは物件価格に対する年間家賃収入の割合を示す指標で、購入時の諸費用や運営にかかる費用は含まれていません。一方、実質利回りは購入時の諸費用や管理費、修繕積立金、固定資産税などの年間費用を差し引いて計算する、より実際の収益性に近い指標です。
実際には投資物件の購入時には、登記費用や不動産取得税、中古物件などでは仲介手数料といった諸費用がかかります。また、固定資産税・都市計画税、賃貸管理手数料のほか、区分所有マンションでは管理費や修繕積立金といった運営コストも発生します。そのため、実際に掛かる費用を加味して、収益性を確認する必要があります。
実質利回りは、こうした購入時の諸費用や運営にかかるコストを反映して算出する利回りです。
実質利回りの計算方法
実質利回りの計算式は、以下のとおりです。
| ■実質利回りの計算式 実質利回り(%)=(年間家賃収入-年間諸費用)÷(物件購入価格+購入時諸費用)×100 |
先ほどの2つの例に、購入時に初期費用としてかかる諸費用や維持費などの年間コストを加えて、実質利回りを計算します。
| 物件1 | ⚫︎物件購入価格:3,000万円 ⚫︎年間想定家賃収入:150万円 ⚫︎年間諸費用:48万円 ⚫︎購入時諸費用:240万円 |
| 物件2 | ⚫︎物件購入価格:5,000万円 ⚫︎年間想定家賃収入:200万円 ⚫︎年間諸費用:24万円 ⚫︎購入時諸費用:300万円 |
物件1:(150万円-48万円)÷(3,000万円+240万円)×100=3.15%
物件2:(200万円-24万円)÷(5,000万円+300万円)×100=3.32%
この例では購入時の諸費用や年間コストを踏まえた実質利回りは「物件1」よりも「物件2」の方が高く、収益性が高いといえます。
表面利回りでは収益性が高く見える物件も、実質利回りでは劣ることがあるため、投資物件を検討する際には実質利回りを計算して比較することが大切です。
表面利回りだけでは見えない不動産投資にかかる2種類の費用

不動産投資にかかる費用を理解しておくことで、表面利回りだけではなく、実質利回りを計算できます。不動産投資にかかる費用について、不動産購入時にかかる初期費用と不動産購入後にかかる年間コストに分けてみていきます。
不動産購入時にかかる初期費用
不動産購入時には、主に以下のような費用がかかります。
| 費用項目 | 内容 |
| 仲介手数料 | ・主に中古物件で、物件を仲介した不動産会社に支払う費用 ・物件価格が400万円を超える場合の計算式は「(物件価格×3%+6万円)+消費税」 |
| 不動産登記費用 | ・不動産移転登記 ・不動産投資ローンを利用する場合の抵当権設定登記に関わる登録免許税 ・司法書士報酬 |
| 不動産取得税 | 不動産を取得したときに課税される税金 |
| ローン融資手数料 | 不動産投資ローンを利用する金融機関に支払う手数料 |
| 収入印紙代 | 売買契約書やローン契約書(金銭消費貸借契約書)に貼付する収入印紙代 |
| 固定資産税・都市計画税 | ・その年の税金を、引き渡し日を境に売主と買主で日割りで負担するのが一般的 |
| 火災保険・地震保険料 | ・不動産投資ローンの利用にあたって火災保険への加入は必須 ・地震保険は任意 |
| 修繕積立金基金 | 新築の区分所有マンションでは、修繕積立金の一時金を徴収することがある |
不動産購入後にかかる年間コスト
不動産購入時には、以下のようなコストがかかります。
| 費用項目 | 内容 |
| 管理手数料 | 区分所有マンションは賃貸管理、一棟物件は賃貸管理・建物管理の費用として、管理会社に支払う費用 |
| 管理費 | 区分所有マンションで建物管理のために徴収される費用 |
| 水道光熱費 | 一棟物件の共用部分で発生する水道代や電気代 |
| 修繕積立金 | 区分所有マンションで共用部分の修繕のために徴収される費用 |
| 修繕費用 | ・退去時の修繕費用、定期的なメンテナンス費用、空室対策のためのリフォーム費用など ・一棟物件は建物全体、区分所有マンションは専有部分が対象 |
| 固定資産税・都市計画税 | ・毎年1月1日の不動産の所有者に課税される税金 ・固定資産税は全物件、都市計画税は市街化区域に立地する物件が対象 |
【物件タイプ別】不動産投資の理想の利回り

不動産投資の理想の利回りは、物件のタイプや築年数によって大きく異なります。例えば、新築物件は購入価格が高くなるため利回りは低くなる傾向にありますが、大規模な修繕費用が当面かからず、空室リスクも抑えられる点が大きなメリットです。
一方で中古物件は価格が安い分、高い利回りを期待できますが、突発的な修繕のリスクや入居者募集の難易度も考慮して運用する必要があります。以下の表で物件タイプ別の理想的な利回りの目安をまとめましたので、ぜひ参考にしてみてください。
| 物件タイプ | 新築 | 中古 |
| 区分マンション | 3~4% | ・築20年程度:5.5% ・築20年超:7~8% |
| 一棟アパート | 8% | 9~10% |
| 一棟マンション | 6% | 7~8% |
| 一戸建て | 10% | 15% |
特に一戸建ては、地域や立地による価格差が大きいため、利回りの振れ幅も大きい傾向にあります。利回りの理想や最低ラインについては、以下の記事でさらに詳しく解説していますので、併せてご覧ください。
【関連記事】不動産投資の利回りは何%が理想?計算方法や相場、注意点をわかりやすく解説
不動産投資の表面利回りにおいて気をつけるポイント

不動産投資において、利回りで気をつけるべきポイントに、以下の3つがあげられます。
- 複数の利回りを計算して比較する
- 実質利回りと融資金利の差も考慮する
- 利回りは変動するものであることを理解する
それぞれ詳しく解説します。
複数の利回りを計算して比較する
利回りには表面利回りや想定利回り、実質利回りなどの種類がありますが、投資物件のポータルサイトや不動産会社のサイトなどに掲載されている物件情報の利回りは、いずれに該当するのか不明瞭なことがあります。
そこで、掲載されている利回りの数字で物件を比較するのではなく、物件情報に記載された賃料や物件価格などから、自分で利回りを計算して比較することがポイントです。また、掲載されている家賃の妥当性についても、確認する必要があります。
実質利回りと融資金利の差も考慮する
不動産投資ローンを利用する場合には、実質利回りを計算して求めるだけでなく、実質利回りと融資金利の差を考慮することが大切です。実質利回りと融資金利の差が大きいほど、効率のよい投資となるためです。
実質利回りと融資の金利の差は、イールドギャップと呼ばれるものです。実質利回りが4%、融資金利が2%というケースでは、イールドギャップは2%となります。イールドギャップを3%程度は確保することを目安として、物件選定の際の判断基準の一つとしましょう。
利回りは変動するものであることを理解する
購入時の利回りが高くても、継続的に続くというわけではなく、変動していくのが一般的です。そのため、購入時点の利回りを維持できることを前提に運用計画を立てるのはリスクがある点を理解しておきましょう。
家賃の下落による利回りの低下を招く要因として、経年劣化による建物の老朽化のほか、周辺エリアの人口減少による賃貸需要の低下、自然災害による建物の損壊などがあげられます。
そこで、定期的なメンテナンスを行って物件の状態を維持できれば、建物の老朽化による家賃の下落を緩和できます。また、大規模リフォームを行えば家賃アップも見込めるでしょう。大規模なリフォームではなくても、入居者が無料で利用できるWi-Fi環境の整備や宅配ボックスの設置、TVモニター付きインターホンへの変更など、入居者に喜ばれる設備を導入するといった方法もあげられます。
高利回り物件を見つけたときにチェックすべき3つのポイント

必ずしも高利回り物件が優良物件というわけではなく、利回りの高さだけを基準に物件を選ぶのは避けるべきです。高利回りの物件は「物件価格が相場よりも安い物件」や「家賃が相場よりも高い物件」の可能性があり、何かしらのリスクが潜んでいるためです。
高利回り物件を見つけたときに、見極めるための以下の3つのチェックポイントがあります。
- 建物や設備の状態
- 告知事項の有無
- 建築条件の確認
それぞれ詳しく解説します。
建物や設備の状態
建物や設備は老朽化が進んで傷んだ状態ではないか、全体的にチェックを行い、修繕が必要な箇所を把握します。
物件資料の写真などで確認するほか、具体的に購入を検討する場合は、実際に現地に足を運んでチェックを行うのが基本です。また、設備に関しては、不動産会社にメンテナンス履歴を確認してもらいます。
現地では、建物の外壁にひび割れ、タイルの浮きや剥がれはないか、手摺などの鉄部に錆びや腐食がないか確認します。室内の壁紙にカビが生えていたら、漏水が起きている可能性があります。また、室内の壁紙や床材などの状態もチェックするべきポイントです。
設備の面では、キッチンや浴室、トイレなどの水回り設備は、交換が必要となる状態か判断するために確認が必要です。古い物件では、浴室にバランス釜が設置されていることがありますが、バランス釜の物件は敬遠されがちです。
建物や設備の老朽化が著しいケースや古い設備が設置されているケースは、そのままの状態では空室期間が長引いてしまいやすいことから、多額の修繕費用を要することが考えられます。
告知事項の有無
告知事項のなかでも重要なのは、過去に殺人や自殺、孤独死といった心理的瑕疵となる事件・事故が起きていないかという点です。売買においては、他殺や自殺、不慮の事故を除く事故死、原因不明の死、不慮の事故や自然死でも特殊清掃が行われたケースは、売主に無期限の告知義務があります。不動産会社を通じて告知事項があれば伝えられますが、念のために確認しましょう。
また、賃貸では、借主へ事件・事故の発生から3年程度の告知義務があり、問い合わせがあったケースや社会的な影響が大きい事件であったケースなどでは、3年を超えても告知義務は残ります。そのため、心理的瑕疵のある事故物件は入居者づけや将来的な売却に苦労することが考えられます。
参考:国土交通省|宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン
建築条件の確認
高利回り物件を見つけたら、再建築不可物件や違法建築が行われている物件ではないか確認します。
再建築不可物件とは、建築基準法で都市計画区域と準都市計画区域に立地する建物で義務付けられている、幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接する接道義務を満たしていない物件です。建築基準法や都市計画法が制定される前に建てられた古い建物のなかには、接道義務を果たしていないものが存在します。
違法建築とは、建築基準法や条例に違反している物件のことです。建築確認をとらずに建てられたケースや建築確認申請の際の建築計画と異なる建物を建てたケースのほか、増改築によって違法建築となったケースもあります。主に建ぺい率や容積率のオーバー、都市計画で定められた用途地域の規定への違反などがあげられます。
再建築不可物件や違法建築は法的瑕疵として売主に告知義務があるため、不動産会社を通じて伝えるのが一般的です。念のために不動産会社に確認するほか、役所に問い合わせるという方法もあります。あるいは、再建築不可物件は、実際に現地で道路への接道幅を測れば確認できます。違法建築は、役所で建築計画概要書の交付を受け、現況と照合して確認する方法もありますが、専門的な知識が必要となるため、建築士などの専門家に調査を依頼するのがおすすめです。
再建築不可物件や違法建築は、不動産投資ローンなどの融資を受けて購入するのが難しく、売却の難しさから出口戦略に苦戦しやすいこともデメリットです。
不動産投資で高利回り物件が抱える5つのリスク

不動産投資において「高利回り」という言葉は魅力的ですが、その裏には理由があることが多いです。具体的には、以下のようなリスクを抱えている可能性があります。
- 満室時の想定により実質利回りとの差が大きくなる
- 需要が低い可能性がある
- 購入後に修繕・維持管理に費用がかかる可能性がある
- 瑕疵物件である可能性がある
- 売却時に買い手が見つかりにくい
それぞれ詳しく解説します。
満室時の想定により実質利回りとの差が大きくなる
高利回り物件の多くは、常に満室であることを前提とした表面利回り(または想定利回り)で計算されていることが多いです。しかし実際の運用では、空室の発生や諸経費の支払いがあるため、手元に残る収益から算出する「実質利回り」が大幅に下がる可能性があります。
特に築年数が経過した物件や駅から遠いなど立地条件の良くない物件では、常時満室を維持することは現実的ではありません。一般的に、不動産投資では年間10~20%程度の空室率を見込む必要があるとされています。さらに、そこから以下のような諸費用を差し引く必要があります。
- 管理費
- 修繕積立金
- 固定資産税
- 火災保険料
このように、購入前に見ていた表面利回りと実質利回りには、大きな差が生じることを理解しておく必要があります。
需要が低い可能性がある
高利回りが設定されている物件は、何らかの理由で物件価格が安く抑えられている可能性があります。その理由の一つが、賃貸需要の低いエリアに立地している可能性です。
例えば、人口減少が進む地方都市や交通の便が悪い郊外、周辺に大学や企業がなく賃貸ニーズが見込みにくい住宅地などがあげられます。こうしたエリアでは空室期間が長期化しやすく、一度退去が発生すると次の入居者を見つけるまでに時間がかかるケースが多いです。
さらに、将来的な家賃下落のリスクも高くなります。需要の低いエリアの物件は、売却しようとしてもなかなか買主が見つからず、出口戦略で苦労する可能性も考慮しなければなりません。
購入後に修繕・維持管理に費用がかかる可能性がある
高利回り物件は築年数が古いケースが多く、外見上はきれいに見えても、建物の構造部分や給排水管、各種設備に老朽化が進んでいる可能性があります。そのため、購入後すぐに給排水設備の交換や屋根・外壁の修繕、エレベーターのメンテナンスなど、想定外の修繕費用が発生するリスクを抱えています。
特に一棟アパートや一棟マンションの場合、共用部分の修繕費用はすべてオーナーの負担となり、一度に高額な出費が発生することも多いです。表面的な利回りの数字だけに惑わされず、購入前に建物の状態を詳細に調査し、将来的な修繕計画や設備投資の必要性まで含めた収支計画を立てることが重要です。
瑕疵物件である可能性がある
提示されている利回りが周辺相場と比べて著しく高い場合、その物件が何らかの「瑕疵(かし)」を抱えている可能性を疑う必要があります。瑕疵とは、物件が通常備えるべき品質や性能を欠いている状態のことで、主に以下の4つに分類されます。
- 心理的瑕疵(過去の事故死や自殺)
- 物理的瑕疵(雨漏り、シロアリ被害、給排水設備の不具合、アスベスト使用など)
- 法的瑕疵(建築基準法違反、再建築不可物件、容積率オーバーなど)
- 環境的瑕疵(火葬場や工場、騒音施設の近接など)
これらの瑕疵がある物件は入居者に敬遠され、空室の長期化や相場より低い家賃設定を余儀なくされる原因になることが多いです。高利回りの裏には必ず何らかの理由があることを理解し、検討段階で瑕疵の有無を不動産会社にヒアリングしておきましょう。
売却時に買い手が見つかりにくい
高利回り物件は、将来売却する際に買い手が見つかりにくいというリスクを抱えています。立地条件の悪さや建物の古さ、管理状態の問題といった高利回りの要因は、そのまま売却時の障害となるからです。
特に、地方の築古物件や再建築不可物件、旧耐震基準で建てられた物件などは、金融機関からの融資が受けにくいため、購入者が現金で購入できる人に限定されてしまいます。買い手候補が少なければ、売却活動は長期化しがちです。
その間の維持管理費もかさみ、最終的には想定より大幅に安い価格で手放さざるを得なくなる可能性もあります。不動産投資では出口戦略も重要な要素であり、将来の売却可能性まで見据えて物件を選ぶことが大切です。
表面利回りが低くても購入に向いている物件の特徴

低利回りの物件のなかにも、以下のような不動産投資に向いている物件があります。
- 利便性が高く人気のエリアであること
- 物件のメンテナンスが行き届いていること
- 安定的な賃料収入が期待できること
それぞれ詳しく解説します。
利便性が高く人気のエリアであること
低利回り物件のなかでも、都市部の人気エリアに立地し、最寄り駅から近いなど利便性の高い物件は、購入を検討するべき物件です。
人気エリアの利便性が高い物件は、賃貸需要の高さから入居者が見つかりやすく、出口戦略においても買主が見つかりやすいことが理由としてあげられます。資産価値が維持しやすいため、家賃が下落しにくく、月々のキャッシュフローによる利益がわずかでも、資産形成の手段となります。また、資産性が高い物件は、低い金利で融資を受けやすいのも特徴の一つです。
ただし、低利回りでイールドギャップが低く、空室が発生すると、すぐにキャッシュフローがマイナスになるような物件は避けるようにしましょう。
物件のメンテナンスが行き届いていること
低利回り物件でも、外壁塗装工事や屋上防水工事などの定期的なメンテナンスや退去時の原状回復工事が適切に実施されているなど、メンテナンスが行き届いている物件は、検討対象となります。
高利回り物件でも、老朽化が進んでいて大がかりな修繕工事が必要な物件は多額の修繕費用が掛かったり、賃貸に出した後に設備などにトラブルが起きて出費がかさんだりする可能性があります。これに対して、メンテナンスが行き届いている物件であれば、大きな費用をかけることなく、すぐに賃貸に出せます。
安定的な賃料収入が期待できること
表面利回りの数値が低くても、長期間にわたって安定した賃料収入が見込める物件は、投資対象として価値が高いと言えます。例えば、単身者向け物件と比較して入居期間が長くなる傾向にあるファミリー向けマンションや、質の高い設備で人気の分譲賃貸マンションは、頻繁な入退去による空室リスクや原状回復費用を抑えられます。
また、官公庁や大手企業の社宅需要、大学の近くで学生の入居が安定しているエリアなども、継続的な収入を得やすいでしょう。
このように需要と供給のバランスが取れているエリアの物件は、急激な不動産価値や家賃の下落が起こりにくく、長期的な収益予測を立てやすいというメリットがあります。表面利回りの高さだけでなく、入居者の属性や地域特性を深く分析することで、安定した収益基盤を持つ優良物件を見つけることが重要です。
不動産投資で利回り以外に重要視すべき3つのこと

不動産投資では高い利回りに目が行きがちですが、長期的に安定した収益を得られる物件を手にするには、以下のようなポイントも欠かせません。
- 周辺の賃貸需要や物件価値
- 物件の管理状況や建物の品質
- 信頼できる不動産投資会社との連携
それぞれ詳しく解説します。
周辺の賃貸需要や物件価値
表面利回りの数字がどれだけ高くても、収益性が持続可能でなければ意味がありません。長期的に安定した収益が見込めるかは、対象のエリアにおいて「ここで暮らしたい」「生活しやすそう」と思う人が将来にわたって存在するかが重要です。例えば、以下のような特徴のある立地・エリアであれば、入居者の住みやすさに直結し、安定した賃貸需要を生み出すでしょう。
- 最寄り駅からの徒歩時間
- 急行列車の停車の有無
- スーパーや病院といった生活利便施設の充実度
また、周辺の人口動態や世帯構成、大学や企業の立地状況も参考になります。ターゲットとなる入居者層が将来にわたって継続的に確保できるかを分析することで、長期的な安定運用へとつながります。ただし、これらの調査は個人では限界があるため、自身で確認しつつ、地域の情報に精通した不動産会社に話を聞くのがおすすめです。
物件の管理状況や建物の品質
建物の管理状況や品質は、将来発生する修繕費用や空室リスクに影響するため、表面利回りでは見えない重要な判断材料になります。中古物件の場合、以下のような建物の現状や情報を確認して、適切な管理が行われているかを確認しましょう。
【現地でチェックできるポイント】
- 外壁の状態
- エントランスやエレベーター内などの共用部分の清掃状況
- 駐輪場やゴミ置き場の使われ方
【物件の書類や不動産会社へのヒアリングで確認するポイント】
- 過去のメンテナンス履歴
- 今後の大規模修繕の実施時期
- 修繕積立金の積立状況
質の高い管理は入居者満足度を高め、長期入居にもつながるため、管理会社の体制まで確認することが望ましいです。また、過去のメンテナンスや修繕積立金に関しては、将来の大きな出費を予測するうえで欠かせない情報ですので、必ず確認するようにしましょう。
信頼できる不動産投資会社との連携
不動産投資の成功には、信頼できる不動産投資会社との関係構築が欠かせません。優良な会社は、物件選定時に表面利回りだけでなく、立地分析や建物調査、詳細な収支シミュレーションなど、多角的な視点から投資判断をサポートしてくれます。
また、購入後の賃貸管理や将来的な売却サポートまで行ってくれる会社もあります。顧客の悩みや投資目的に寄り添って対応してくれる会社を選ぶことで、表面利回りの数字だけに惑わされない資産運用を実現できるでしょう。
不動産投資会社を探す際には、過去の運用実績やサービス内容を確認することが大切です。なお、不動産投資の失敗原因と成功するためのポイントについては、以下の記事でも詳しく解説しているので、併せてご覧ください。
【関連記事】失敗の原因と成功するためのポイントを解説
毎年多くのお客様がトーシンパートナーズでマンション経営をスタートしています
月々1万円でローリスク&ロングリターンな資産運用

将来に漠然とした不安を抱えてはいるものの、なにをしたらよいかわからない……。
トーシンパートナーズではそんなお悩みを抱えるみなさまに、マンション経営をご案内しています。
マンション経営と聞くと空室の発生や、家賃の下落・滞納・資産価値の下落などの不安要素が思い浮かぶかもしれません。ですがパートナーとなる会社次第で、ご不安は限りなくゼロに近づけることができます。
家族のために、自分のために、未来の安心のために、ローリスク&ロングリターンな資産運用を始めてみませんか?
Amazonギフト券
プレゼント限定キャンペーン
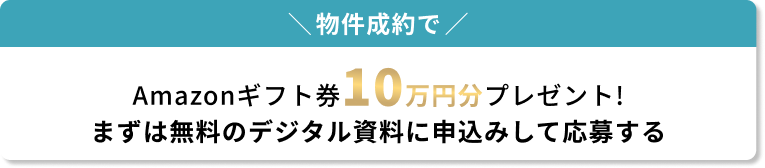
プレゼント適用条件はこちら
≪特典付与の条件≫
- ■キャンペーン名
- 不動産投資マンションご成約でAmazonギフトプレゼントキャンペーン
- ■キャンペーン概要
- トーシンパートナーズで不動産投資マンションをご成約いただいた方へ、もれなく10万分のAmazonギフトをプレゼント。
- ■キャンペーン対象期間
- 2025年11月5日~2026年2月28日
- ■キャンペーン対象条件
- 以下のすべての条件に該当する方
- 2026年2月28日までに資料請求、2026年3月31日までにご購入された方。
- 専用フォームからお申し込みいただいた方
※その他の方法でお申し込みの方は対象外です。 - キャンペーン期間中に初めてトーシンパートナーズで不動産投資マンションをご成約いただいた方。
- ■注意事項
- 本キャンペーンはトーシンパートナーズによる提供です。
- Amazonギフトのお受け取りは、お一人様1回限り10万円です。
- Amazonギフトは、物件購入のお申込みいただき、決済完了後の1か月以内にシリアルコードで送付予定となります。
- 本キャンペーンについてのお問い合わせはAmazonではお受けしておりません。
トーシンパートナーズマーケティング事務局【support@tohshin.co.jp】までお願いいたします。 - Amazon、Amazon.co.jpおよびそれらのロゴはAmazon.com,Inc.またはその関連会社の商標です。
まとめ

利回りには表面利回りや想定利回りといった指標もありますが、投資物件を選ぶときに用いるべきなのは実質利回りです。不動産投資に掛かる費用を理解しておくことで、実質利回りを計算できます。ただし、実質利回りと融資金利との差であるイールドギャップを考慮するなど、利回りで気をつけるポイントもあります。また、高利回り物件が必ずしも投資物件として優れているわけではなく、低利回り物件の中にも購入を検討するべき物件があることも理解しておきましょう。
不動産投資の表面利回りに関してよくある質問

不動産投資の表面利回りに関してよくある質問は、以下の3つです。
- 表面利回りと実質利回りの違いは何?
- 表面利回り何%以上なら投資する価値があるのか?
- 表面利回りが低い物件でも投資する価値はあるのか?
それぞれ詳しく解説します。
Q1. 表面利回りと実質利回りの違いは何?
表面利回りは、年間の家賃収入を物件の購入価格で割っただけのシンプルな指標で、諸経費は一切考慮されていません。一方、実質利回りは、年間の家賃収入から管理費、修繕積立金、固定資産税といった運営費用を差し引き、さらに物件の購入時にかかった仲介手数料や登記費用なども含めて計算します。
そのため、より実際の収益性に近い現実的な指標と言えます。例えば、広告に「表面利回り5%」と記載されていても、諸費用を考慮した実質利回りは3〜4%程度になることが一般的です。不動産投資の収益性を正確に判断するためには、必ず実質利回りを重視するようにしましょう。
Q2. 表面利回り何%以上なら投資する価値があるのか?
投資価値があると言える表面利回りの基準は、物件のタイプやエリア、築年数によって大きく異なるため、一概に「何%以上」と断言できません。例えば、区分マンションの場合、新築なら3〜4%、築20年程度の中古で5.5%、築20年を超える物件なら7〜8%程度が理想的な利回りの目安とされます。
一方で一棟アパートであれば新築で8%、中古なら9〜10%と、より高い利回りが期待できます。重要なのは、提示された表面利回りの数字の高さだけで判断しないことです。その利回りが実現可能なのか、立地条件や建物の状態、将来性といった要素を総合的に評価し、投資価値を見極める必要があります。
Q3. 表面利回りが低い物件でも投資する価値はあるのか?
はい、表面利回りが低くても、投資価値の高い物件は存在します。特に、以下の条件を満たす物件は、長期的な資産形成の観点から魅力的と言えるでしょう。
- 立地の優位性:都市部の人気エリアで駅近など、賃貸需要が安定している
- 資産価値の維持:将来的な売却時にも買い手が見つかりやすく、資産価値が下落しにくい
- 管理状況良好:適切なメンテナンスが行われ、長期的な修繕費用を抑えられる
- 安定した入居者層:ファミリー世帯や長期入居が見込める属性の入居者が多い
特に都心部の好立地物件は、表面利回りの数値は低くなる傾向にあります。しかし、空室リスクが低く資産価値も安定しているため、長期的な資産形成を目的とする投資には非常に有効な選択肢となります。