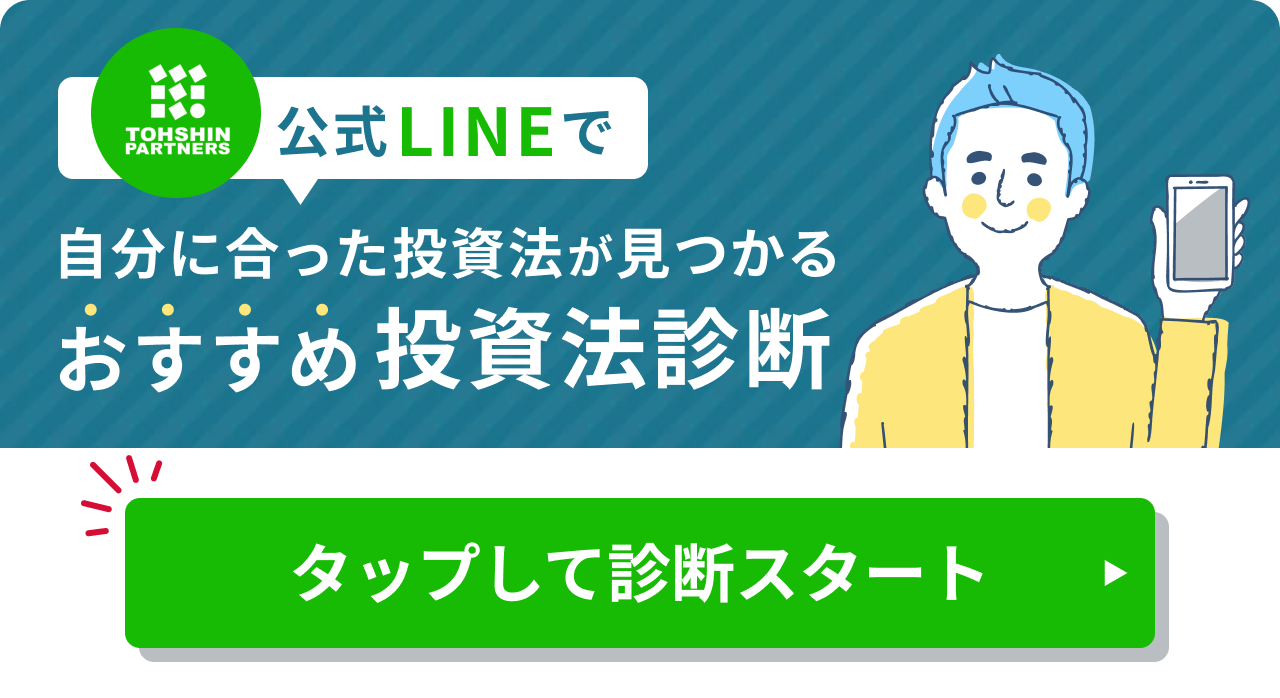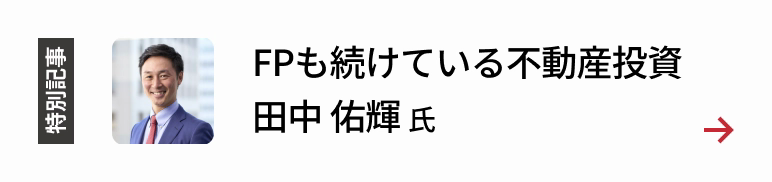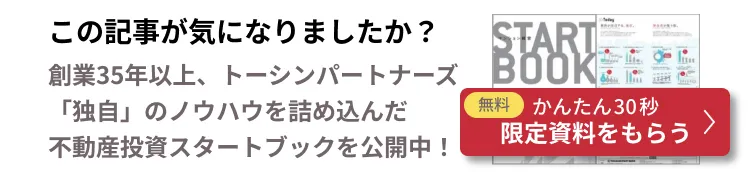- 不動産投資のリスク
不動産投資詐欺の主要な10の手口を紹介|よくある誘い文句や身を守る対策も紹介

不動産投資詐欺について、詐欺の種類や誘い文句、怪しい不動産会社の特徴などを詳しく知りたいと思っている人は多いのではないでしょうか。具体的な誘い文句や怪しい不動産会社の特徴などを事前に押さえておけば、不動産投資詐欺に遭うリスクを軽減でき、安心して不動産投資を進められるでしょう。
本記事では、不動産投資詐欺の種類やよくある誘い文句、怪しい不動産会社の特徴などについて解説します。
不動産投資詐欺の主要な10の手口

不動産投資詐欺の種類や特徴を知っておくと、リスクに備えやすくなります。それぞれの種類について、見ていきましょう。
| 【不動産投資詐欺の主要な手口】 |
|---|
| ・手付金詐欺 |
| ・入居状況詐欺 |
| ・婚活・デート情報詐欺 |
| ・海外不動産投資詐欺 |
| ・二重譲渡詐欺 |
| ・サブリース詐欺 |
| ・囲い込み |
| ・地面師詐欺 |
| ・二重売買契約 |
| ・クラウドファンディング詐欺 |
不動産投資のリスクとメリットがゼロからわかる、スタートブックの無料プレゼントはこちら
手付金詐欺
不動産投資詐欺の一つとして挙げられるのが、手付金詐欺です。手付金詐欺は、「この物件は、高利回りで、立地もよいため、すぐに売れてしまいます。手付金を入れてキープしていたほうが絶対にいいですよ!」などと説明して手付金を払わせ、その後連絡が取れなくなるのが特徴です。
物件の購入はおろか、手付金の回収もできません。手付金の支払いを強引に迫ってくるような営業担当者・不動産会社は詐欺の可能性が高いため、相手にしてはいけません。
また、信頼できる不動産会社であるかを判断する際の材料として、宅地建物取引業の免許の有無や取引実績も確認しましょう。
入居状況詐欺
入居状況詐欺とは、実際は空室が多い物件でありながらも、入居率が高いように装った詐欺のことです。投資家は、当初予定していた収益を得られず、大きな損失を被る可能性があります。具体的な詐欺の手口として、以下のようなものがあげられます。
- サクラに入居してもらい入居率が高いように見せる
- 資料の入居率を改ざんして高く見せる
- 「満室である」と嘘をついて資料の利回りを高く見せる
このような嘘で新たなオーナーを探して、物件の入居状況がよいことをアピールします。この詐欺を見抜くための対策として、物件の現地確認を必ず行い、実際の入居状況を目視で確認しましょう。また、管理会社や近隣の不動産会社に相場家賃や空室率について問い合わせることも有効です。
入居状況の偽装は外部から見抜くことが困難なため、信頼できる不動産会社を選ぶことが重要な防御策となります。複数の業者から情報を収集し、異常に高い利回りを謳う物件については特に慎重に検討しましょう。
婚活・デート情報詐欺
婚活・デート情報詐欺とは、マッチングアプリや婚活サイトなどを利用し、恋愛感情を悪用した詐欺で、デートなどを繰り返し、親密になったタイミングで不動産の購入を勧めるものです。親密になると冷静な判断ができなくなるため、条件の悪い不動産を勧められて購入してしまいます。
購入後は連絡が取れなくなり、初めて詐欺に遭ったことに気づきます。特に、短期間で親密になった人から不動産購入を勧められた場合は、詐欺を疑うようにしましょう。
海外不動産投資詐欺
海外不動産投資詐欺は、実在しない物件を販売したり、実際よりも高値で販売したりする詐欺のことです。海外の不動産投資では、日本国内よりも利回りが高い物件が多くあります。ただし、海外不動産は現地確認が難しいことを逆手に取り、詐欺を行うケースがあります。特に豪華なパンフレットやホームページの情報、営業担当者の説明だけで購入を決断するのはリスクが高いです。
契約する前には、できれば実際に現地で物件の有無を調べた上で、説明を受けた情報と相違点がないかを確認しましょう。
二重譲渡詐欺
二重譲渡詐欺とは、すでに売却済みの物件を別の人に販売する詐欺のことです。すでに売却済みであることを伏せて販売を行い、手付金や代金を受け取った後、連絡が取れなくなるという手口です。代金を支払った後に、実際には別の人が既に所有権を取得していることが判明し、購入者は物件も代金も失うという深刻な被害を受けます。
二重譲渡詐欺を防ぐためには、契約前に法務局で不動産登記簿謄本を取得し、現在の所有者や抵当権の設定状況を必ず確認し、信頼できる不動産会社を選びましょう。
サブリース詐欺
サブリースとはいわゆる「又貸し」のことで、不動産オーナーが入居者と賃貸借契約を結ぶわけではなく、オーナーと管理会社が直接賃貸借契約を結び、契約上入居者となる管理会社がオーナーに対して家賃を支払う管理形態の一つです。
その際、管理会社はオーナーに対して家賃保証を行うことが多く、一般的に家賃の8~9割程度が保証されます。不動産投資においてもっとも大きなリスクの一つである「空室リスク」を回避する手段として有効で、仮に所有する物件に空室が発生した場合でも家賃収入を得られるメリットがあります。
ここで注意したいのが、保証率は変動しない一方で、物件状況や賃貸需要などに応じて「賃料は見直される」という点です。
サブリース詐欺とは、「空室になっても毎月ずっと10万円が確実に保証される」「保証額は1円も下がらないので安定経営できる」といった嘘をついて契約を勧める詐欺のことです。
サブリース詐欺では保証される金額(= 管理会社から支払われる家賃)が変動する場合がある事実を意図的に隠し、「確実に9万円保証される」などと、あたかも金額が永久に保証されるような話しぶりで騙そうとしてきます。
家賃保証サービスには条件や期間などの制限があるため、契約書をよく読み、契約内容を十分に理解した上で検討しましょう。
サブリース詐欺の被害に遭わないためにも、信頼できる不動産会社を選び、きちんと説明してくれる担当者から購入することが大切です。あまりにも利回りが高く、条件がよすぎる物件には注意してください。
囲い込み
囲い込みとは、「他社を検討するなら、この条件では難しい」「◯◯社は条件が悪いのでやめたほうがいい」など、強引な営業手法や他社を批判することで自社以外の不動産会社の選択肢をなくし、購入や売却の機会を損失させる手法です。
こういった状況に直面した場合は、営業担当者の言葉が本当に自分のためを思ってのことかを冷静に考えるべきでしょう。不動産投資は長期運用が基本です。検討中の期間よりも運用中の期間のほうが圧倒的に長いため、目の前の利益に安易に飛びつかないようにしましょう。
地面師詐欺
地面師詐欺とは、他人の土地や建物を自分の所有物であるかのように偽装して、不正に売却し、代金をだまし取る詐欺行為です。犯行はグループで行われることが多く、非常に巧妙な手口なため、不動産取引の専門家でもだまされる可能性があります。
アパートやマンション、土地などは、外観を見ただけでは所有者がわからず、法務局の登記簿で確認する必要があります。そのため投資家は、売主から提示された偽の不動産登記書類や本人確認書類を信じ、契約してしまう可能性があるのです。
登記する際に詐欺に遭ったと判明しても、犯行グループの行方はすでに不明となっており、資金をだまし取られる上に物件も入手できない可能性があります。
二重売買契約による詐欺
二重売買契約による詐欺の事例として、不動産の売買契約書を2枚用意して、実際の契約書には正しい金額を、融資を行う金融機関に提出する契約書には実際の金額より高額な金額を記載することで、金融機関から不当に多額の融資を引き出す行為があります。
もし金融機関が金額の偽造に気づくと、買主は借入金の一括返済を求められる可能性があります。
売買契約書には買主の押印が必須ですが、2枚の契約書の金額の違いに気づかないまま買主が押印してしまうことで詐欺行為が可能になってしまうため、買主は売買契約書によく目を通さなければなりません。
クラウドファンディング詐欺
クラウドファンディング詐欺とは、架空の不動産投資案件で投資家をだまし、資金を不正に取得する犯罪行為です。
不動産クラウドファンディングは少額からできる手軽な投資商品として、近年参加者数が増加しています。しかし、インターネットによるクラウドファンディング投資で詐欺被害に遭う方が急増しており、特に無登録または架空業者による勧誘が問題視されています。
「絶対にもうかる」といったうたい文句で営業を行ったり、リスクについて十分な説明がなかったりするケースが多いです。中途解約ができないほか、出資金が持ち逃げされる上にリターンが得られないといった被害が報告されています。
不動産投資詐欺でよくあるこんな誘い文句に注意

不動産投資詐欺でよくある誘い文句を知っていれば、リスクに対して敏感になり、怪しい不動産会社を見分けられるでしょう。具体的には、以下のような誘い文句があります。
- 「節税対策になります」
- 「儲かります」
- 「空室リスクを保証します」
- 「将来確実に値上がりします」
- 「クーリングオフできます」
それぞれ詳しく紹介します。
「節税対策になります」
不動産投資詐欺でよくある誘い文句の一つが「節税対策になります」という言葉です。不動産投資は、節税効果が期待できるのはメリットの一つですが、「必ず節税になる」というわけではありません。
不動産投資は、ローン金利や管理費、減価償却費(物件取得費用を一定期間に分割して計上する費用)などの費用を経費として計上できます。さらに、所得が赤字になった場合は、損益通算(赤字をほかの所得の黒字と相殺する制度)によって総所得額を減らせるため、所得税や住民税を軽減できます。 しかし、不動産投資の所得が黒字の場合は、その分所得税や住民税が高くなります。不動産投資をしても、必ず節税できるわけではないことを理解しておきましょう。
「儲かります」
「この物件であれば、絶対に儲かります」「利回りが高いので、相当儲かります」などと言ってくる担当者や不動産会社には注意しましょう。不動産投資は、「必ず儲かる」というわけではありません。思うように家賃収入を得られず、損をする場合もあります。
不動産会社が「儲かる」と言って提示する利回りは、「表面利回り」であることが多いです。表面利回りとは、年間の家賃収入を物件価格で割って算出した数字のことで、管理費や修繕費、仲介手数料などのコストは考慮されていません。 そのため、表面利回りは実態よりも高い傾向にありますが、利回りを見る際には、コストも考慮された「実質利回り」を参考にする必要があります。不動産投資に限った話ではありませんが、「儲かります」という誘い文句は怪しいことが多いため、十分に注意してください。
「空室リスクを保証します」
「空室が出ても家賃◯万円を保証します」という誘い文句が出たら、不動産投資詐欺の可能性があります。多くの不動産会社が家賃を保証するサブリースを行っていますが、「家賃の◯%」など、保証の基準は率で提示するのが一般的です。
「家賃の◯万円を保証します」のように、金額を基準として保証する会社はありません。あったとしても、期間や上限などの条件が付きます。
家賃保証を金額で伝えてくる不動産会社や担当者には注意しましょう。
「将来確実に値上がりします」
「この物件は、将来確実に値上がりします」「絶対に値上がりするので、大丈夫です」などといった誘い文句には、気を付けましょう。
立地によっては、購入時よりも価値が上がる物件はあります。しかし、そのような物件は少なく、購入時点で「この物件は100%値上がりする」と予測できる人はいません。
「確実」「絶対」「100%」などといった言葉を用いて将来的な値上がりをアピールする担当者や不動産会社の場合は、「怪しい」と判断し、距離を置いたほうがよいでしょう。
「クーリングオフできます」
「クーリングオフできます」という誘い文句にも、注意が必要です。宅建業法において、不動産投資の契約は、クーリングオフが認められています。ただし、クーリングオフの適用には、以下の4つの条件があります。
- 売主が宅建業者である
- 契約を締結した場所が事務所や関連建物以外である
- クーリングオフの説明を受けてから8日以内である
- 物件の引き渡しや代金の支払いがまだである
「クーリングオフができる」といった言葉で安心させて、強引に契約を結ぼうとする担当者や会社には気を付けましょう。
30年分の不動産投資ノウハウを詰め込んだ、スタートブックの無料プレゼントはこちら
不動産投資詐欺の可能性がある怪しい不動産会社の特徴

不動産投資詐欺の可能性がある会社の特徴を知っていると、リスク回避をしやすくなります。怪しい不動産会社の特徴について、見ていきましょう。
| 【怪しい不動産会社の特徴】 |
|---|
| ・強引なスタイルで迫ってくる |
| ・宅建免許を所持していない |
| ・ホームページにリアル感がない |
| ・おとり広告を掲載している |
| ・リスクやデメリットを伝えようとしない |
| ・手付金の支払いを急かしてくる |
| ・現地訪問が難しい遠方の物件ばかりを紹介してくる |
強引なスタイルで迫ってくる
投資家の都合を考えず、営業担当者が以下のような強引な態度で迫ってくる場合は、不動産投資詐欺の可能性があります。
- 「今すぐ決めないと、後悔しますよ!」
- 「今日、ここで絶対決断しましょう!」
- 「後悔しない物件なので、まずは申し込んでください!」
- 「買う・買わないは、今すぐ決めてください!」
無理に決断を求めてきたり、契約するまで事務所などで缶詰め状態にされ、長時間説得を受けたりする場合もあります。投資家の意見もろくに聞かず、押し売りをしてくる不動産会社は、相手にしてはいけません。
信頼のおける不動産投資会社であれば、顧客が十分に検討できる時間を確保し、質問に対して丁寧に回答してくれるはずです。また、一度断ってもしつこく連絡を続けたり、自宅や職場まで押しかけたりするような業者は避けるべきです。
冷静に判断するためにも、複数の業者から話を聞き、家族や信頼できる第三者に相談してから決断しましょう。もし強引な営業を受けた場合は、きっぱりと断り、必要に応じて消費生活センターなどに相談するのがおすすめです。
宅地建物取引業免許を所持していない
不動産の売買や仲介を行うには、宅地建物取引業免許が必要であり、この免許を持たずに営業することは違法行為です。不動産投資を検討する際は、必ず相手業者が正式な免許を取得しているかを確認しましょう。
宅地建物取引業免許番号は「国土交通大臣(○)第○○○○号」や「○○県知事(○)第○○○○号」といった形式で表示されます。カッコ内の数字は免許の更新回数を表しており、数字が大きいほど長期間営業している証拠となります。この免許番号は、会社のホームページや営業担当者の名刺、パンフレットなどに記載されていることが多いので確認してみましょう。
もし免許番号の記載がない場合には、その業者との取引は避けるのが無難です。免許番号が確認できた場合でも、国土交通省の「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」で実際に有効な免許であるかを確認できます。過去に行政処分を受けた業者についても同システムで調べることが可能です。
無免許業者が扱う物件は「物件価格が相場より高い」「利回りが低い」「多額の修繕費用がかかる」など、条件の悪い物件である可能性が高く、投資失敗のリスクが格段に上がります。必ず免許の確認を怠らないようにしましょう。
ホームページにリアル感がない
不動産会社のホームページにリアル感がない場合や、不自然な印象を受ける場合は注意が必要です。具体的には、以下のような状態のホームページです。
- 物件の写真が古い
- 会社代表・社員の写真がない
- 日本語がおかしい
- 情報が会社概要しか載っていない
- 物件情報が長らく更新されていない
- 取引実績が載っていない
- ホームページがやたら古い
- 問い合わせ先が載っていない
上記のようなホームページの不動産会社は、利用しないほうが安全です。詐欺的な行為をする不動産会社ではなかったとしても、現代においてWeb戦略の欠如は、事業の存続に関わる重大な問題といえます。
おとり広告を掲載している
おとり広告を利用して顧客を取り込もうとする業者にも注意が必要です。おとり広告とは、売る意思がない、または、すでに売れてしまった魅力的な物件の広告を利用して、集客をすることをいいます。
投資家に「すでに売れてしまったのでほかの物件を紹介します」などと言い、ほかの物件を押し付けたり個人情報を聞き出したりします。しかし、これは宅地建物取引業法や不動産の表示に関する公正競争規約に違反する行為です。
優良物件の場合は、実際にすぐに買い手が見つかるケースが多いため、話を聞きに行った時には広告の物件が売れていることは珍しくありません。もしもお目当ての物件が売れてしまっていた場合には、勧められるがままに物件を見学するのではなく、一度持ち帰って冷静に検討することが大切です。
リスクやデメリットを伝えようとしない
優良な不動産投資会社は、投資にはリスクが伴うことを必ず説明し、物件のデメリットも包み隠さず伝えます。一方、怪しい業者は「絶対に儲かる」「リスクはない」といった甘い言葉で勧誘し、空室リスクや修繕費用、金利上昇リスクなどの説明を避ける傾向があります。
さらに、顧客が家賃下落の可能性や地域の将来性についての質問をしても「心配ありません」「大丈夫ですよ」など、曖昧な回答しか得られない場合は注意が必要です。投資には必ずリスクが伴うため、デメリットの説明を避けたり「大丈夫です」としか答えなかったりする業者とは契約を避けるべきでしょう。
手付金の支払いを急かしてくる
悪質な不動産投資会社の典型的な手口として、手付金の支払いを急かすことがあります。例えば「今日中に決めないと他の人に取られる」「特別価格は今だけ」と顧客を煽り、冷静な判断をする時間を与えないのが特徴です。しかし通常、不動産取引では十分な検討期間が設けられるべきで、急かされる理由はありません。
不動産は一点物のため、検討中に他の人が購入する可能性があるのは事実ですが、業者が顧客を急かす行為は、宅地建物取引業法における不当行為に該当します(※)。信頼できる業者であれば、顧客の検討時間を十分に確保してくれるはずです。決断を急かされた場合は、その業者との契約は避けるのが賢明です。
(※)参考:宅地建物取引業法施行規則|第十六条の十一
現地訪問が難しい遠方の物件ばかりを紹介する
詐欺的な不動産投資会社は、投資家が現地確認しにくい遠方の物件ばかりを勧める傾向にあります。手口としては「地方は利回りが高い」「人口減少地域だからこそチャンス」といった理由で、実際には需要が見込めない立地の物件を販売しようとします。
現地確認が困難なことを悪用し、周辺環境や建物の状態について虚偽の説明をしたり、写真を加工して実際より良く見せたりするケースもあります。優良な業者であれば、契約前に現地見学を勧めたり、詳細な現地レポートを提供したりするはずです。遠方の物件を検討する際は、必ず現地視察を行い、地元の不動産業者や管理会社からも情報収集することが重要です。
不動産投資詐欺から身を守る7つの対策

不動産投資詐欺から身を守る対策として、以下7つがあげられます。
- 信頼できる法律家を事前に探しておく
- 実績のある管理会社に依頼する
- リスクの説明を明確にしてくれない業者は信頼しない
- 不動産投資の知識を身に付ける
- 不明点・疑問点は必ず解消する
- 現地調査を行う
- 不動産投資の人脈を築く
不動産投資詐欺に引っかからないようにするための方法について、見ていきましょう。
信頼できる法律家を事前に探しておく
不動産投資詐欺に引っかからないためには、信頼できる法律家を事前に探しておきましょう。弁護士や法律事務所を事前に探しておけば、トラブルに巻き込まれた場合に早期解決を目指せます。
また、専門的なアドバイスがもらえるため、不動産投資詐欺の被害を最小限に抑えられる上、早めに相談すれば未然に防ぐことも可能です。
ただし、法律家といっても専門分野があるため、不動産投資に精通している弁護士や法律事務所を選ぶのがおすすめです。
実績のある管理会社に依頼する
実績のある管理会社に依頼すると、トラブルを回避しやすくなります。実績のある管理会社は、たくさんの不動産投資に関わってきた経験があるため、多くの情報やノウハウを持っています。
怪しい不動産会社とやり取りしていると、「不動産投資詐欺の可能性がある」などといったアドバイスをくれる可能性があります。
また、オーナーが貸借人と直接契約を結ぶと、なんらかのトラブルが起きた際にオーナーの負担が大きくなります。管理会社が間に入っていれば、貸借人とのやり取りは管理会社が行うため、オーナーの負担を軽減することが可能です。
毎月管理委託手数料を支払う必要はあるものの、管理業務やトラブル対応などを任せられるため、多くのオーナーが管理会社に業務を委託しています。
リスクの説明を明確にしてくれない業者は信頼しない
不動産投資について、メリットや都合のよいことのみを話し、リスクやデメリットについて伝えない業者を信用するのは危険です。
どのような物件を選んだとしても、不動産投資には必ずリスクがあります。メリットばかりを強調し、デメリットやリスクにほとんど触れない不動産会社は、顧客のことを第一に考えず、「とにかく物件を売りたい」「ノルマを達成したい」などといった自社の都合ばかり考えている可能性が高いです。
デメリットやリスクをきちんと説明してくれる不動産会社を選べば、不動産投資詐欺のリスクを軽減できるでしょう。
不動産投資の知識を身に付ける
不動産投資は専門的な知識がなくても始められますが、詐欺被害に遭わないためにはできるだけ知識を付けておくことをおすすめします。
初心者向けの書籍が多数販売されているため、読みやすいものを選んで不動産投資の全体的なイメージをつかみましょう。インターネット上でも不動産投資に関するニュースや記事を見つけられます。
ほかにも、不動産投資会社が開催している無料セミナーや相談会などもおすすめです。しかし、こういったイベントを利用している悪質な業者もいるため、主催元が健全な経営を行っているか、公式サイトなどで確認してから申し込みましょう。
不明点・疑問点は必ず解消する
不動産投資会社と相談している間に、不明な点や疑問に思う点があった場合は、うやむやにせず、その場で解決してから次のステップに進むことが大切です。理解していないまま担当者に言われるがまま契約まで進めてしまうと、自分にとって不利な契約になる可能性があるためです。
信頼できる担当者であれば、不明点や疑問点についてわかりやすく説明し、真摯に対応してくれるでしょう。不明点などを尋ねることは、よい不動産投資会社を選ぶためのポイントにもなる上に、詐欺対策にも役立ちます。
現地調査を行う
不動産投資におけるリスクを最小限に抑えるために、現地調査を行うのも良いでしょう。購入物件の場所によっては確認に出向くのが難しいケースもありますが、詐欺のリスクを減らすため、可能な限り現地を確認することをおすすめします。
現地調査をすれば、写真を見ただけではわからない情報も入手できます。例えば、外壁のひび割れや塗料のはがれ、共用エリアの管理状況のほか、物件の立地条件や周辺環境などもチェック可能です。
詐欺対策だけでなく、よりよい物件を購入するためにも現地調査が役に立ちます。
不動産投資の人脈を築く
不動産投資をしている、または目指している同志や、経験豊富な成功者とのつながりを持つことで、有益な情報やアドバイスを得られることがあります。購入を検討している物件を相談すると、「それは詐欺かもしれない」といったアドバイスが受けられるかもしれません。
初心者がひとりで得られる情報には限りがあります。自分では気が付かないリスクに気づけるよう、ネットワークづくりをしておくとよいでしょう。
安心して任せられる不動産投資会社を選ぶ判断基準
不動産投資詐欺に遭わないために、不動産投資会社は慎重に検討する必要があります。安心して任せられる会社を選ぶには、以下の特徴に注目するのが大切です。
- 創業が長く売買実績が多い
- 多くの金融機関と取引がある
- 賃貸管理も行っている
信頼できる不動産投資会社の特徴を理解して、詐欺被害を未然に防ぎましょう。
創業が長く売買実績が多い
業歴が長い不動産投資会社は、これまで多くの取引を行ってきていることから、堅実な経営を行っていると考えられます。仮に詐欺行為をしている場合、一つの場所にとどまり長く営業を続けることはできないためです。
また、販売実績についても確認し、多くの取引経験があるところを選びましょう。事業規模や従業員数、販売実績などは公式サイトで確認できます。
多くの金融機関と取引がある
取引可能な銀行数が多い不動産投資会社は、信頼できるという判断の一つになります。銀行によっては不動産投資に対し消極的なところが少なくなく、そういった中で取引銀行が多いのは、信用されている証だからです。
銀行により融資限度額や貸付条件などが異なるため、投資家ごとに適した銀行の選択肢が多いのはメリットです。
賃貸管理も行っている
不動産投資会社は、物件の販売のみではなく賃貸管理も行っているところを選ぶことも良いでしょう。
物件の購入から購入後の管理まで一貫して委託可能であれば、長期にわたるトータルサポートを受け続けることができます。また、販売のみを行っている不動産投資会社より、幅広い実践的なアドバイスを得ることも可能です。
不動産投資詐欺に遭ったときの相談先

不動産投資詐欺に遭ったときの相談先は、以下の4つが挙げられます。
| 【不動産投資詐欺に遭ったときの相談先】 |
|---|
| ・免許行政庁 |
| ・宅地建物取引業保証協会 |
| ・消費生活センター |
| ・弁護士 |
これらの相談先に連絡して不動産投資詐欺の件を伝えれば、対処法についてアドバイスがもらえます。不動産会社に対しては、免許行政庁や宅地建物取引業保証協会などから厳しいペナルティを課されるでしょう。
被害に遭ったときだけでなく、「この不動産会社は詐欺行為をしているかもしれない」と感じたら、すぐに相談しましょう。
免許行政庁
不動産業者は、国土交通大臣または都道府県知事から宅地建物取引業の免許を受けて営業しています。免許行政庁は、宅地建物取引業の免許を交付する行政機関であり、業者の不正行為に対する監督権限を持っています。不正行為を行った業者に対しては、業務停止処分や免許取消処分などの行政処分を行うことが可能です。そのため、悪質な業者に遭遇した場合は、免許行政庁に相談・通報することが有効な手段となります。
相談する際は、契約書や重要事項説明書、やり取りの記録などの資料を準備し、具体的な被害状況を説明することが重要です。ただし、免許行政庁の対応は業者への処分が中心となるため、直接的な金銭的救済は期待できません。なお、具体的な相談窓口は、業者の免許番号から管轄する行政庁を確認できます。
宅地建物取引業保証協会
宅地建物取引業保証協会は、不動産取引の安全性を確保するために設立された公益法人です。全国に「全国宅地建物取引業保証協会」と「不動産保証協会」の2つの保証協会があり、多くの不動産業者がいずれかに加入しています。
万が一、協会に加入している業者との取引で損害を受けた場合、弁済業務保証金から損害額の弁済を受けられる制度があります。被害を受けた場合は、協会に苦情を申し出て解決を図りましょう。ただし、弁済限度額は業者の事務所数によって決まっており(主たる事務所のみの場合1,000万円、支店が1か所あれば1,500万円など)、被害額全額が補償されない可能性もあります。
消費生活センター
消費生活センターは、消費者被害全般について相談できる公的機関で、不動産投資詐欺に関する相談も可能です。センターは全国に設置されており、消費者ホットライン「188」に電話すれば最寄りの相談窓口につながります。
相談は無料で、中立的な立場から専門の相談員が被害状況を聞き取り、適切なアドバイスや解決方法を提案してくれます。同様の被害事例に基づく経験豊富な助言を受けられるため、1人で悩まずに早めに頼ることが重要です。ただし消費生活センターは相談・助言が中心となり、直接的な金銭回収や法的措置については、必要に応じて弁護士や警察などの専門機関を紹介されることがあります。
弁護士
不動産投資詐欺の被害が深刻な場合、弁護士への相談が確実な解決手段となります。弁護士は法的な観点から被害を分析し、民事訴訟や刑事告発などの適切な法的手続きを選択できます。契約の無効や取消し、損害賠償請求など、具体的な被害回復に向けた戦略を立てることが可能です。
また、不動産や投資詐欺に詳しい弁護士を選びましょう。各地の弁護士会で法律相談や弁護士紹介を受けられるほか、日弁連の『ひまわりサーチ』で弁護士を検索することも可能です。弁護士への相談は一般的に有料ですが、法テラスの無料法律相談の利用や成功報酬制を採用している弁護士への相談で、負担を軽減できる場合があります。早期の相談が解決の可能性を高めるため、被害が疑われる段階でも相談を検討しましょう。
参考:日本弁護士連合会|弁護士情報提供サービス ひまわりサーチ
参考:日本司法支援センター|法テラス
毎年多くのお客様がトーシンパートナーズでマンション経営をスタートしています
月々1万円でローリスク&ロングリターンな資産運用

将来に漠然とした不安を抱えてはいるものの、なにをしたらよいかわからない……。
トーシンパートナーズではそんなお悩みを抱えるみなさまに、マンション経営をご案内しています。
マンション経営と聞くと空室の発生や、家賃の下落・滞納・資産価値の下落などの不安要素が思い浮かぶかもしれません。ですがパートナーとなる会社次第で、ご不安は限りなくゼロに近づけることができます。
家族のために、自分のために、未来の安心のために、ローリスク&ロングリターンな資産運用を始めてみませんか?
Amazonギフト券
プレゼント限定キャンペーン
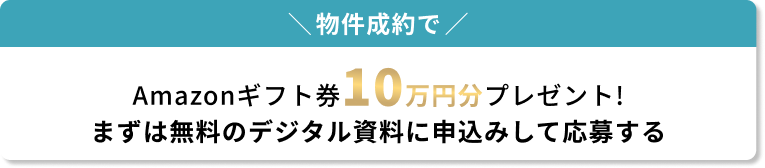
プレゼント適用条件はこちら
≪特典付与の条件≫
- ■キャンペーン名
- 不動産投資マンションご成約でAmazonギフトプレゼントキャンペーン
- ■キャンペーン概要
- トーシンパートナーズで不動産投資マンションをご成約いただいた方へ、もれなく10万分のAmazonギフトをプレゼント。
- ■キャンペーン対象期間
- 2025年11月5日~2026年2月28日
- ■キャンペーン対象条件
- 以下のすべての条件に該当する方
- 2026年2月28日までに資料請求、2026年3月31日までにご購入された方。
- 専用フォームからお申し込みいただいた方
※その他の方法でお申し込みの方は対象外です。 - キャンペーン期間中に初めてトーシンパートナーズで不動産投資マンションをご成約いただいた方。
- ■注意事項
- 本キャンペーンはトーシンパートナーズによる提供です。
- Amazonギフトのお受け取りは、お一人様1回限り10万円です。
- Amazonギフトは、物件購入のお申込みいただき、決済完了後の1か月以内にシリアルコードで送付予定となります。
- 本キャンペーンについてのお問い合わせはAmazonではお受けしておりません。
トーシンパートナーズマーケティング事務局【support@tohshin.co.jp】までお願いいたします。 - Amazon、Amazon.co.jpおよびそれらのロゴはAmazon.com,Inc.またはその関連会社の商標です。
まとめ

ここでは、不動産投資詐欺の種類、よくある誘い文句、怪しい不動産会社の特徴などについて解説しました。よくある誘い文句や怪しい不動産会社の特徴に当てはまる営業担当者・不動産会社を見つけたら、相手にしないようにしましょう。相手にすると、不動産投資の被害に遭い、大きな損害を被るリスクがあります。
不動産投資には、詐欺のリスクがあることも想定した上で、不動産会社や物件を選び、運用することが大切です。
FAQ
Q1. 不動産投資の勧誘で「絶対に儲かる」と言われた場合、本当に信頼できるのでしょうか?
A.
「絶対に儲かる」「利回り◯%保証」といった甘い誘い文句は、詐欺案件で多く使われます。たいていは 表面利回りのみ提示し、実質利回りやコストについて言及しない手口です。信頼できる会社であれば、 リスクや経費を含めた現実的な数字を提示し、丁寧な説明を行います。
表面利回りとは?不動産投資初心者が注意すべき利回りの落とし穴と物件選定のポイント
Q2. 「手付金を早く払えば確保できる」など急かされるのは、なぜ危険なのでしょうか?
A.
急かす営業は手付金詐欺の典型です。話を聞く前や調査前に現金を求められた場合、その後連絡が取れなくなるリスクがあります。安心安全な取引では、契約前に検討時間を十分に確保するのが普通です。
Q3. 管理会社から「家賃ずっと保証します」と言われたが、本当でしょうか?
A.
いわゆる サブリース詐欺では、「契約期間中ずっと家賃◯万円保証」と虚偽を唱えます。実際には、保証額は変動する場合が多く、上限や見直し条項があるのが一般的です。一見魅力的でも、契約条件を細部まで確認し、必要であれば専門家へ相談することが重要です。