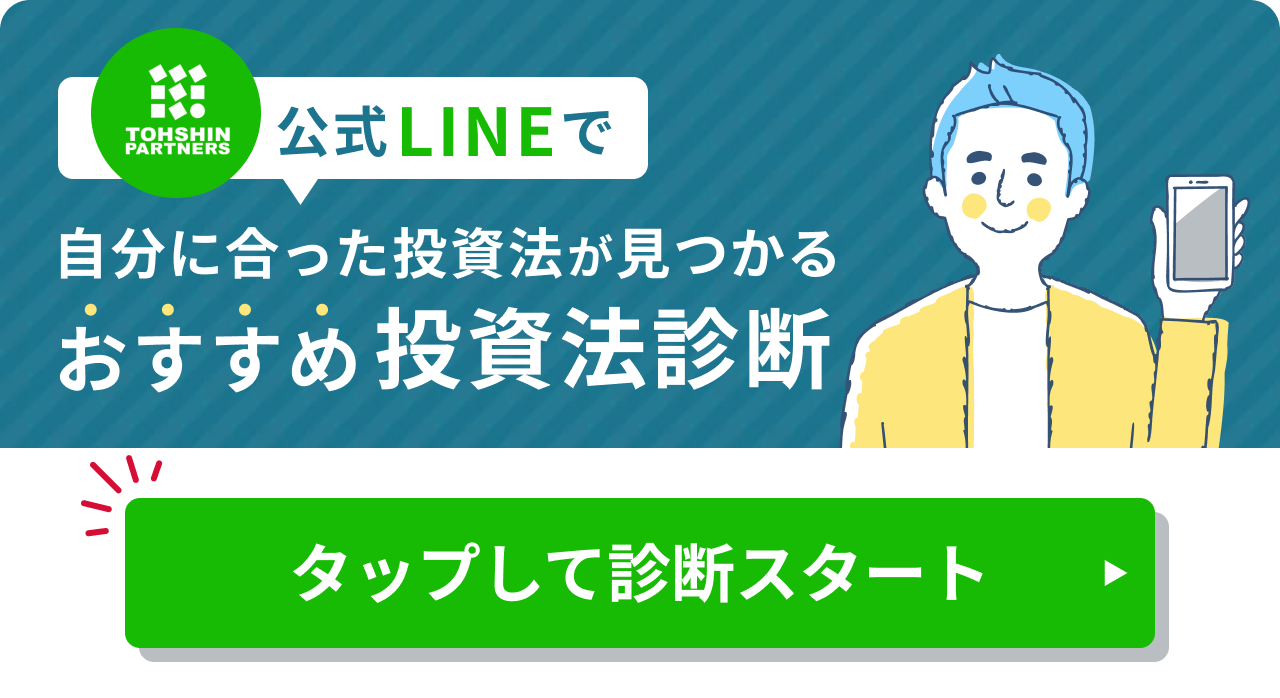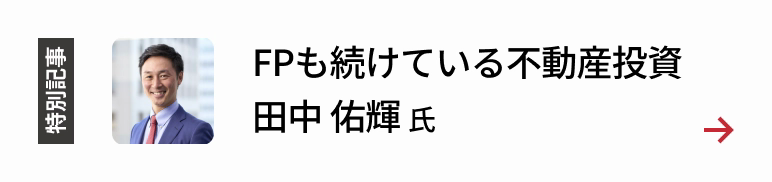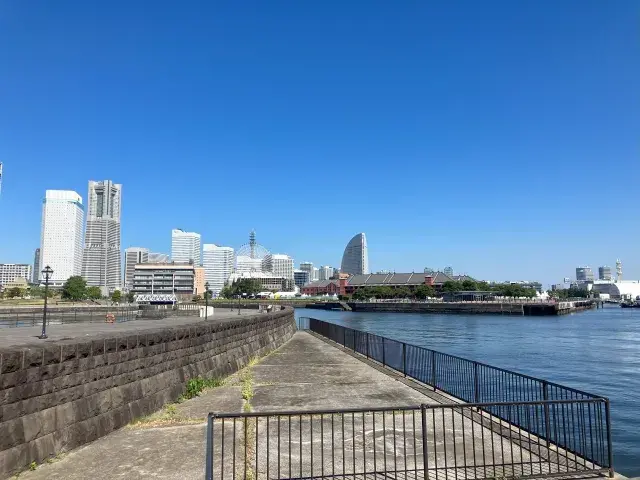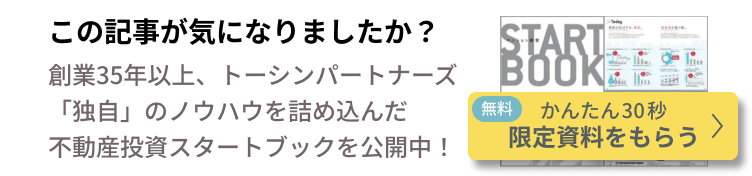- 不動産投資の基礎知識
賃貸管理の手数料の相場を3つの契約形態ごとに解説!失敗しない管理会社の選び方も紹介

賃貸管理会社を選ぶとき「手数料が安い会社のほうが得」と考える方が多いのではないでしょうか。しかし実際には、安さだけを基準に賃貸管理会社を選んだことで、思わぬトラブルやコスト増につながるケースもあります。
この記事では、賃貸管理の手数料の相場を契約形態ごとに解説します。金額だけで管理会社を決めるのが危険な理由や失敗しない選び方まで紹介するので、ぜひ最後までご覧ください。
賃貸管理の手数料に含まれる業務

賃貸管理会社に支払う手数料には、さまざまな業務が含まれており、大きく分けて「入居者募集」と「契約後の管理」に分かれます。入居者募集では、以下の業務を委託することが可能です。
- 募集広告の掲載
- 問い合わせ対応
- 内見の調整
- 契約書類の作成
これらは「リーシング」と呼ばれるもので、空室を埋めるうえで欠かせない業務です。一方で入居後の管理では、以下のような事務手続きを代行します。
- 毎月の家賃集金
- 滞納時の督促
- 契約の更新手続き
- 入居者からの問い合わせやクレーム対応
- 設備不良が発生した際の初期対応
ただし工事や設備の修繕については、手数料とは別に都度費用が発生するのが一般的であり、契約前に業務範囲をよく確認しておくことが重要です。管理会社ごとに対応範囲が異なるため、手数料の金額だけで判断しないように注意しましょう。
契約形態ごとの手数料の相場を解説
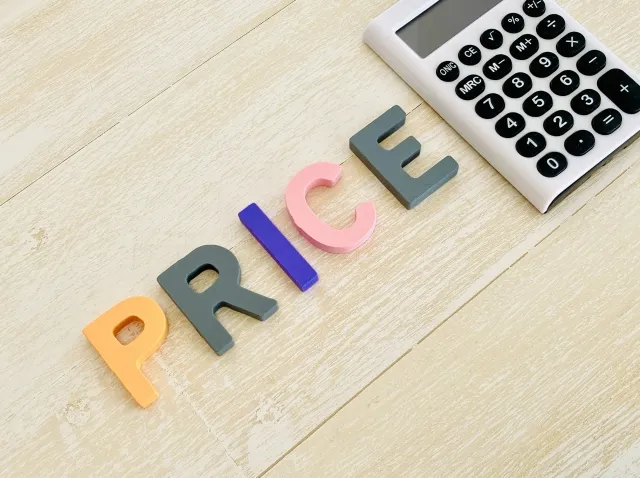
賃貸管理の契約形態によって、管理会社に支払う手数料の相場や業務内容は大きく異なります。それぞれの特徴を把握することで、自身に合った管理スタイルを選ぶ判断材料になるでしょう。この章では、契約形態ごとの手数料の相場について詳しく解説します。
集金代行型は3〜5%
集金代行型は、家賃の回収や滞納者への督促といった事務作業を中心に委託する契約形態です。入居者からのクレーム対応や設備の修繕といった「建物管理」は含まれません。賃貸管理会社へ委託する業務範囲が限定的であるため、手数料は3〜5%と比較的低めに設定されています。
ただし、入居者対応や建物の点検などは対象外となるため、オーナー自身での対応が求められます。手間の軽減は限定的であるものの、空室が少なく入居者トラブルも少ない物件のオーナーにとっては、必要な部分だけを絞って委託できるため、コストと業務負担のバランスが取りやすい選択肢といえるでしょう。
建物管理型は5〜7%
建物管理型は家賃の集金に加え、以下のような建物全体の維持管理を任せられる契約形態です。
- 入居者からの設備不良の連絡窓口
- 廊下やゴミ置き場などの共用部の定期清掃
- 照明や消火器などの設備の点検・交換
手数料の相場は5〜7%で、これらの業務を一任できるため、オーナーが現地に赴いて対応する必要はほとんどありません。たとえば、夜間の水漏れトラブルで入居者から管理会社に連絡があった場合、管理会社が修理業者を手配し、立ち会い・報告まで対応します。
また、ゴミ出しルール違反への注意喚起や、近隣トラブルの初期なども含まれるケースが多く、物件の運営における実務のほとんどを委託できる点が魅力です。手数料はやや高めになりますが、遠方に住んでいて現場での対応が難しいオーナーには、収益と負担の両面から見ても、有力な選択肢となるでしょう。
サブリース契約は10〜20%
サブリース契約では、管理会社が物件を一括で借り上げ、オーナーには毎月決まった金額の家賃が支払われます。空室の有無にかかわらず家賃収入が得られる点が特徴で、手数料の相場は10〜20%と比較的高めに設定されています。
この契約形態は、入居者対応や建物管理などの業務をすべて任せられるため、運用にかかる手間を抑えたいオーナーに適しているでしょう。ただし、契約内容によっては途中解約が難しい場合や、他の契約形態と比較して収益性が低くなる可能性もあります。
安定収入を重視する反面、契約中の途中解約ができないなど柔軟性に欠ける場合もあります。契約前に家賃保証の条件や免責期間など、不明点がないように内容を確認しておくことが重要です。
賃貸管理会社を手数料の金額だけで選ぶのが危険な4つの理由

賃貸管理会社を選ぶ際に、手数料の安さだけで判断してしまうと、思わぬトラブルや負担が生じることがあります。ここでは、賃貸管理会社を手数料の金額だけで選ぶのが危険な理由を詳しく解説します。
管理の質が良くない可能性がある
手数料の安さばかりを優先すると、実際には提供されるサービスが必要最低限にとどまり、入居者対応や設備管理など通常期待される管理業務が十分に実施されないケースもあります。例えば、クレーム対応や設備不具合への初期対応が遅れると、入居者の満足度が低下し、早期退去による空室リスクの拡大につながることがあります。
対応履歴の管理や書類の整備が不十分だと、別の担当者が引き継ぐ際に情報が足りず、トラブルが長期化する恐れもあるでしょう。金額の安さだけで判断してしまうと、結果的にオーナー自身の収益や手間に悪影響を及ぼす可能性もあるため、管理体制の整備状況をしっかりと見極めることが重要です。
高額な追加費用を請求されるケースがある
手数料を安く見せながら、実際には別名目で高額な費用が発生するケースもあります。例えば、原状回復費や広告費などが「オプション」として別料金で請求される場合もあり、想定よりも運用コストが膨らみキャッシュフローが悪化することもあるでしょう。
別料金が契約時に明示されていなかったり、金額の上限が不明確だったりする場合には、収支計画そのものが崩れてしまう恐れがあります。また料金体系が不透明な場合、費用の妥当性を判断できず、収益性が低下する可能性もあります。契約前には、手数料に含まれる業務範囲と、追加費用が発生する条件と金額まで確認することが重要です。
解約などの条件が厳しい場合がある
賃貸管理会社との契約では、解約条件が厳しく設定されているケースもあります。例えば「10年未満の解約は違約金が発生する」「更新時以外は解約できない」といった制限が設けられていると、他社への乗り換えを進めにくいでしょう。
また、解約時に入居者の契約書の引き渡しが滞ったり、鍵の受け渡しに時間がかかったりすると、入居募集や管理業務の引き継ぎにも支障が出ます。こうしたリスクを防ぐために、複数社の契約内容を比較し、業界内での相場や条件を把握できると安心です。
工事会社が選べないことがある
管理手数料が安い場合でも、その他のコストがかさむケースもあります。特に注意したいのが、原状回復工事や修繕作業などを管理会社が指定する業者に限定している契約です。管理会社の利益が上乗せされることで、相場よりも高い費用が請求される可能性があります。
高額な工事費用でトータルでの支出が増え、収支を圧迫する原因になります。契約前には、手数料だけでなく「どの工事が、いくらかかるのか」「依頼先の選択肢はあるのか」といった点まで確認することが重要です。手数料の安さだけに注目せず、長期的なトータルコストで比較検討する視点を持ちましょう。
失敗しない賃貸管理会社の選び方3選
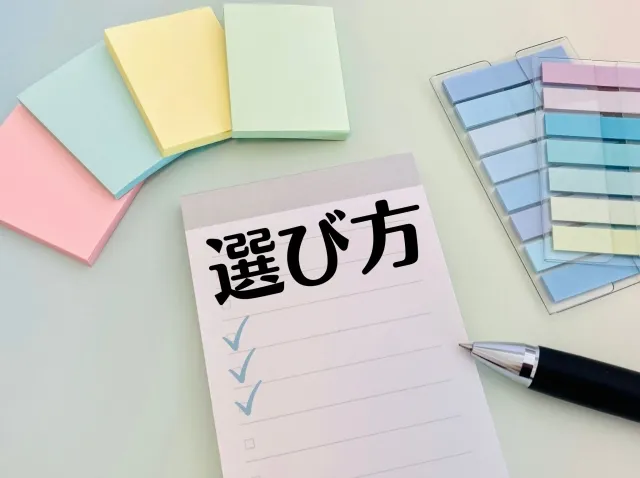
管理会社を選ぶ際、費用面の条件だけで判断したことで、想定外のトラブルや出費が発生する可能性があります。長期的に安定した賃貸経営を行うためには、実績や体制など複数の観点から総合的に判断することが大切です。ここでは、失敗しない賃貸管理会社の選び方を詳しく解説します。
入居率や管理実績をチェックする
入居率は、管理会社の募集力や空室対策の実力を判断するうえで重要な指標です。一般的に95%以上の入居率がある会社は、安定した運用体制が整っていると考えられます。また、地域ごとの特性やニーズを正しく捉えている管理会社ほど、的確な広告展開やターゲット設定が可能です。
入居率のほかにも、どのような物件を管理しているか、直近の空室改善事例などを確認すると、会社の状況や対応方法を把握しやすくなります。信頼できる管理会社は、公式サイトやパンフレットなどで実績を積極的に開示しているケースが多く「どんな情報を発信しているか」もひとつの判断材料になるでしょう。
料金と管理内容のバランスを確認する
管理手数料の金額だけでは、管理会社の対応力や業務範囲を正確に把握することはできません。たとえ月額費用が抑えられていたとしても、必要な業務が別料金になる場合は、結果的に高くついてしまうこともあります。手数料がやや高めでも「入居者対応」「家賃督促」などの幅広い業務が含まれていれば、コストパフォーマンスが高いといえるでしょう。
契約前には、見積書や契約書の記載内容を読み込み、業務範囲と費用の内訳を照らし合わせて検討することが重要です。特に、広告料や緊急対応の有無などは見落とされがちなので、将来的な支出に関連するポイントを注意して確認しておきましょう。
対応力と信頼感のある担当者がいるかを見極める
管理会社を選ぶ際は、手数料や実績だけでなく、担当者との相性や対応力も重要な判断材料です。問い合わせに対して、迅速かつ丁寧に対応してくれるかどうかは、その会社の姿勢を知る手がかりになります。こちらの意向をしっかりとくみ取り、的確な提案をしてくれる担当者であれば、信頼感も高まるでしょう。
長期的な管理を任せることを考えると、信頼できる人物かどうかの見極めも大切です。例えば説明が一方的だったり、こちらの話を遮るような対応が目立つ場合は、今後のやり取りに不安が残ります。一方で、管理状況の報告体制やトラブル時の対応フローなどを明確に伝えてくれる担当者なら、安心して任せられる可能性が高くなります。
毎年多くのお客様がトーシンパートナーズでマンション経営をスタートしています
月々1万円でローリスク&ロングリターンな資産運用

将来に対して漠然とした不安を抱えているものの「何から始めればいいのかわからない」と感じている方も多いのではないでしょうか。そんな方にこそ、ご紹介したいのがマンション経営という選択肢です。空室の発生や家賃の滞納といったリスクが気になるかもしれませんが、パートナーとなる管理会社を慎重に選べば、不安を抑えることは可能です。
月々1万円から無理なく始められるプランもあり、家計に大きな負担をかけずに将来に備えることができます。ご自身やご家族の将来の安心のために、ローリスク&ロングリターンな資産形成を検討してみてはいかがでしょうか?
Amazonギフト券
プレゼント限定キャンペーン
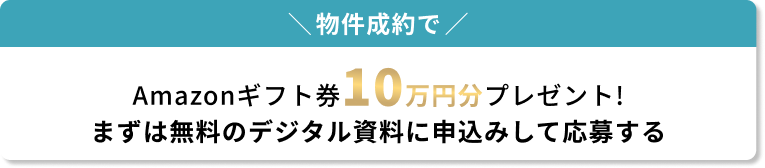
プレゼント適用条件はこちら
≪特典付与の条件≫
- ■キャンペーン名
- 不動産投資マンションご成約でAmazonギフトプレゼントキャンペーン
- ■キャンペーン概要
- トーシンパートナーズで不動産投資マンションをご成約いただいた方へ、もれなく10万分のAmazonギフトをプレゼント。
- ■キャンペーン対象期間
- 2025年11月5日~2026年2月28日
- ■キャンペーン対象条件
- 以下のすべての条件に該当する方
- 2026年2月28日までに資料請求、2026年3月31日までにご購入された方。
- 専用フォームからお申し込みいただいた方
※その他の方法でお申し込みの方は対象外です。 - キャンペーン期間中に初めてトーシンパートナーズで不動産投資マンションをご成約いただいた方。
- ■注意事項
- 本キャンペーンはトーシンパートナーズによる提供です。
- Amazonギフトのお受け取りは、お一人様1回限り10万円です。
- Amazonギフトは、物件購入のお申込みいただき、決済完了後の1か月以内にシリアルコードで送付予定となります。
- 本キャンペーンについてのお問い合わせはAmazonではお受けしておりません。
トーシンパートナーズマーケティング事務局【support@tohshin.co.jp】までお願いいたします。 - Amazon、Amazon.co.jpおよびそれらのロゴはAmazon.com,Inc.またはその関連会社の商標です。
まとめ
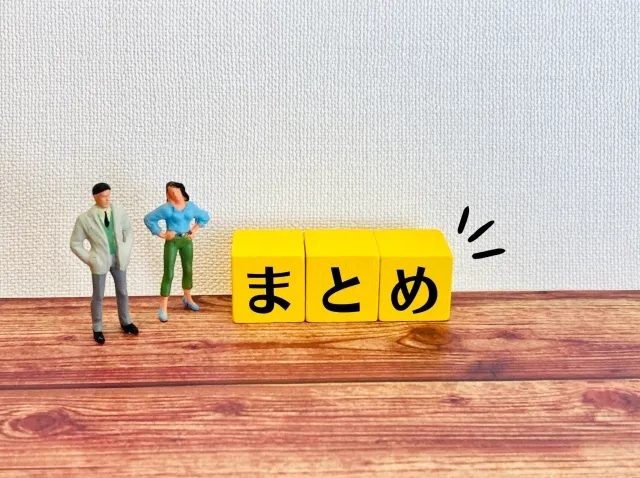
将来への備えとして、堅実に収益を積み重ねられるマンション経営を検討する方が増えています。その第一歩として重要なのが、信頼できる管理会社を選ぶことです。手数料の安さだけにとらわれず、業務範囲や実績、担当者の対応まで総合的に確認することが大切です。
トーシンパートナーズでは、首都圏の人気エリアを中心に、新築ワンルームマンション等への投資プランをご案内しています。資産価値や空室リスクを抑えた運用を目指せるため、老後資金の準備手段として検討してみてはいかがでしょうか。