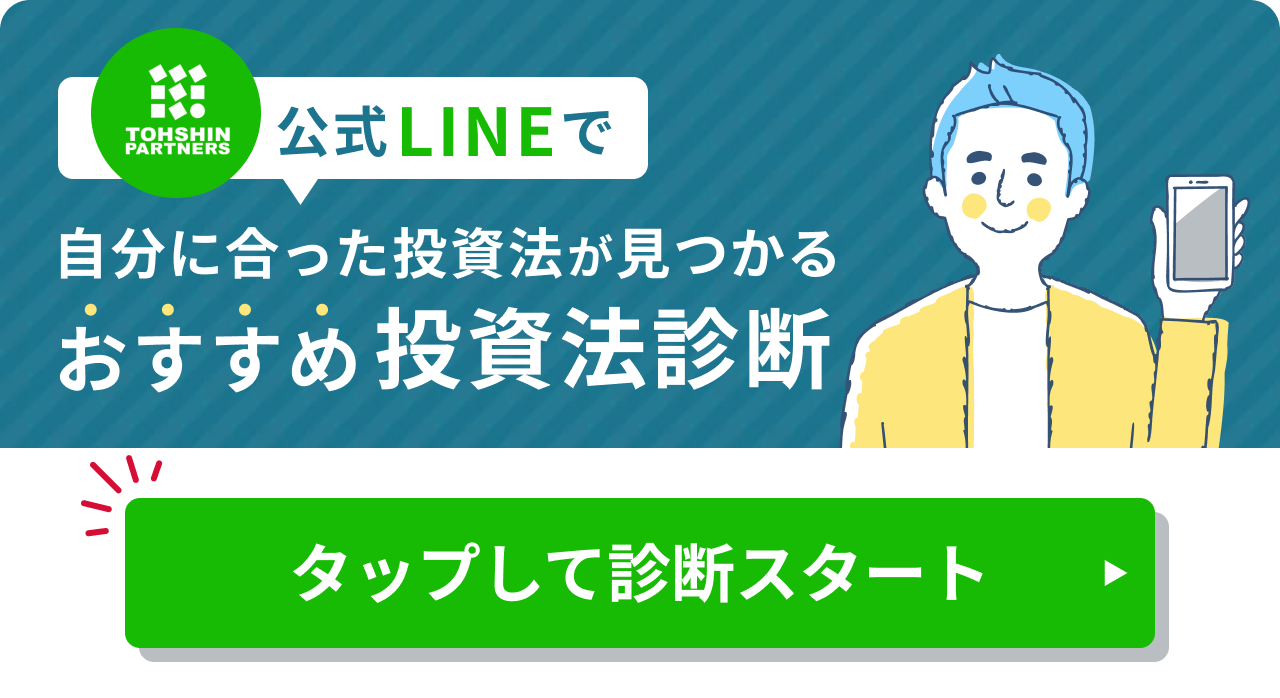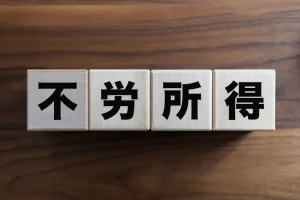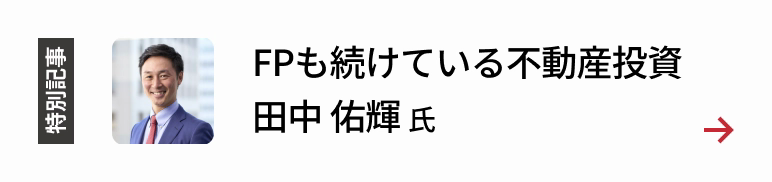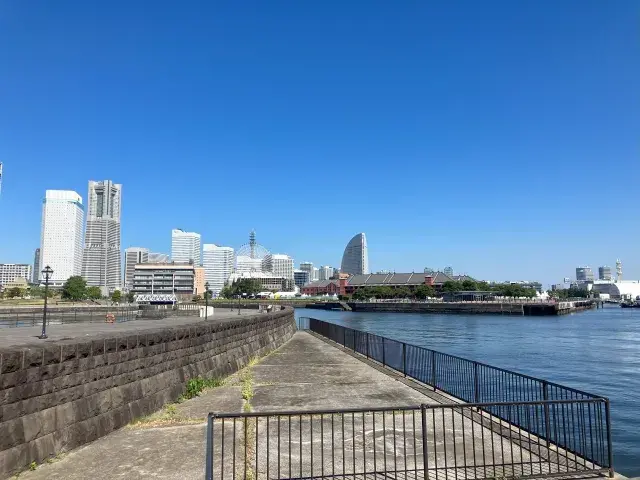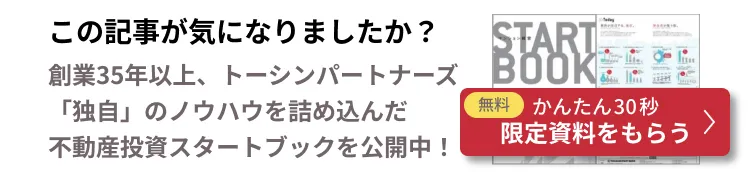- 不動産投資の基礎知識
公務員に保険が不要と言われる理由を解説!制度でカバーできないリスクと対策を紹介
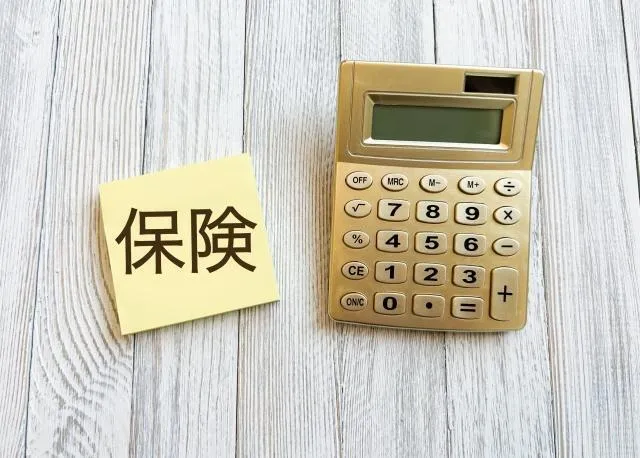
公務員の方のなかには「公務員は保障が手厚いから保険は不要」と聞いたことがあるのではないでしょうか。しかし、本当に保険は不要なのか気になる方は多いです。
この記事では、公務員に保険が不要といわれる理由を整理しつつ、制度ではカバーしきれないリスクや、公務員でも保険が必要になるケースを解説します。また、保険以外にできる将来の備えについても紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。
公務員に民間の保険が不要といわれる理由

公務員に「民間の保険は不要」といわれる理由は大きく分けて以下の2つです。
- 病気やケガによる休職中も手厚いサポートがある
- 割安な団体保険に入れる
それぞれの理由について、詳しくみていきましょう。
病気やケガによる休職中も手厚いサポートがある
公務員に保険が不要といわれる理由の1つに、病気やケガによる休職時の保障が手厚いことが挙げられます。
民間企業では病気やケガで休職した場合は、無給もしくは減額になるケースが一般的です。しかし、公務員には以下のような収入保障制度が整っており、長期療養時も生活への影響を最小限に抑えることができます。
- 病気休暇(最大90日間):給与の100%支給
- 病気休暇終了後の休職(最長1年間):給与の80%支給
さらに、休職期間の満了後も「傷病手当金」により、給与の約60%が一定期間保障される仕組みとなっています。また、公務員に限らず社会保険には「高額療養費制度」という仕組みがあります。これは、月々の医療費が一定額を超えた場合に超過分が払い戻される制度です。
上限額は年齢や所得水準によって異なりますが、たとえば現役世代で年収370〜770万円の世帯であれば、1か月あたりの自己負担上限は8〜10万円程度に抑えられます。
| 適用区分 | ひと月の上限額(世帯ごと) |
|---|---|
| 年収約1,160万円〜 健保:標準報酬月額83万円以上 国保:旧ただし書き所得901万円超 | 252,600円+(医療費−842,000円)×1% |
| 年収約770万〜約1,160万円 健保:標準報酬月額53万〜79万円 国保:旧ただし書き所得600〜901万円 | 167,400円+(医療費−558,000円)×1% |
| 年収約370万〜約770万円 健保:標準報酬月額28万〜50万円 国保:旧ただし書き所得210〜600万円 | 80,100円+(医療費−267,000円)×1% |
| 〜年収約370万円 健保:標準報酬月額26万円以下 国保:旧ただし書き所得210万円以下 | 57,600円 |
| 住民税非課税世帯 | 35,400円 |
このような制度をうまく活用すれば、長期の療養が必要となった場合でも、経済的な負担を抑えて貯蓄の範囲内で対応できるでしょう。
割安な団体保険に入れる
公務員に保険が不要といわれるもう1つの理由に、割安な団体保険に加入できることが挙げられます。
団体保険とは企業や団体が従業員向けに一括で契約する保険で、個人契約に比べて保険料が安く、保障内容も比較的充実しているのが特徴です。公務員の多くはこの団体保険に加入できる仕組みが整っており、手頃な掛金で医療費や万が一のリスクに備えることが可能です。
このように、公務員は団体保険の保障内容が充実していることから「民間の保険にあえて加入しなくても十分」と考える方も少なくありません。
公務員の不動産投資は問題ない?成功させるポイントや副業扱いにならない対処法をご紹介
もぜひチェックしてみてください!
公務員が加入する健康保険は「共済組合」

加入する健康保険の制度は、職業によって異なります。たとえば、会社員であれば「健康保険(協会けんぽや健保組合)」に、個人事業主であれば「国民健康保険」に加入するのが一般的です。そして、公務員が加入するのが「共済組合」になります。
共済組合は他の健康保険制度と比べて、保障内容が手厚いことが特徴で、その1つが「附加給付」と呼ばれる独自の上乗せ保障制度です。附加給付の代表例が「一部負担金払戻金」で、通常の高額療養費制度に加えて、診療報酬明細書1件につき25,000円を超える自己負担分が払い戻される仕組みとなっています。
この制度を活用すれば、最終的な自己負担額は1件あたり25,030円※まで軽減される仕組みです。このように、共済組合は医療費の負担を大きく抑えられるため、公務員にとって手厚い健康保険制度となっています。
※一部負担金払戻金は、25,000円を超える自己負担額が払い戻されますが、端数処理の関係で実質の上限は25,030円程度になることが多いです。
公務員でも保険で備えておきたい3つのリスク

公務員には手厚い保障が用意されていますが、それでもすべてのリスクをカバーできるわけではありません。ここでは、公務員でも保険で備えておきたい3つのリスクについて解説します。
公的保険ではカバーできない医療費負担
公務員は、高額療養費制度や共済組合の一部負担金払戻金といった手厚い保障がありますが、それだけではカバーしきれない医療費も存在します。
たとえば、以下のような費用は公的保険の対象外となるため、全額自己負担となります。
- 先進医療の費用(技術料などは全額自費)
- 自由診療(保険適用外の治療法や薬剤)
- 入院時の差額ベッド代
- 入院中の食事代
- 日用品費(紙おむつ、洗面具など)
- 通院時の交通費(タクシー代・駐車料金など)
こうした費用は、場合によっては数十万〜数百万円にのぼることもあり、貯蓄だけでは対応が難しいケースも考えられます。
退職後の医療費負担
現役の公務員であれば、共済組合を通じて手厚い医療保障を受けることが可能です。しかし、転職や定年退職によって共済組合から離れると「一部負担金払戻金」などの附加給付が受けられなくなり、医療費が増えることになります。
また、定年退職後は年齢とともに通院や入院の頻度が高くなる傾向があり、それに伴って医療費負担も増加しやすくなるでしょう。こうした将来のリスクに備えるためにも、定年後を見据えて民間の医療保険に加入しておくことも有効な選択肢です。
死亡に対するリスク
死亡リスクにも、きちんと備えておく必要があります。公務員が亡くなった場合でも、会社員と同様に受給要件を満たしていれば、遺族基礎年金や遺族厚生年金が支給されます。
しかし、実際には遺族年金があっても現役時代の収入と比べると大幅に減ってしまうケースが一般的です。そうなると、遺された家族がこれまで通りの生活を送るのは難しくなります。教育費や葬儀費用などのことも考慮すると、公的保障だけに頼らず民間の保険や資産形成などで備えることが大切です。
不動産投資は本当に生命保険の代わりになるの?気になる死亡保険との違いを解説
もぜひチェックしてみてください!
公務員でも保険加入が必要なケース

公務員であっても、以下のケースに該当する場合は民間保険の必要性が高いです。
- 家族が増える予定の人
- 貯蓄があまりない人
それぞれの理由について詳しく解説します。
家族が増える予定の人
配偶者やお子さまがいる方、または家族が増える予定のある方は、教育費や生活費の準備とともに保険などで万が一に備えることが重要です。
たとえば、子ども1人を高校まで公立、大学は私立に通わせると想定した場合、教育資金は約1,000万円かかるといわれています。さらに子どもの数が増えれば、その分必要な資金も増加していきます。
こうした将来の支出を見越して、必要な保障額をカバーできる民間保険に加入しておくことが大切です。
貯蓄があまりない人
貯蓄が少ない方は、医療費への備えとして医療保険やがん保険の加入を検討しましょう。
特にがん治療では、手術や入院・通院に加えて、先進医療など保険適用外の高額な治療費が発生することもあります。さらに、治療期間中に仕事を休むことで収入が減り、生活費の負担が増える可能性もあるでしょう。
ある程度の貯蓄があれば対応できるかもしれませんが、貯蓄が十分でない場合には、治療を続けること自体が難しくなる可能性もあります。こうした事態を避けるためにも、がん保険などで治療費や生活費をサポートできるよう、準備しておくことが大切です。
公務員が保険以外にできる備え・資産形成
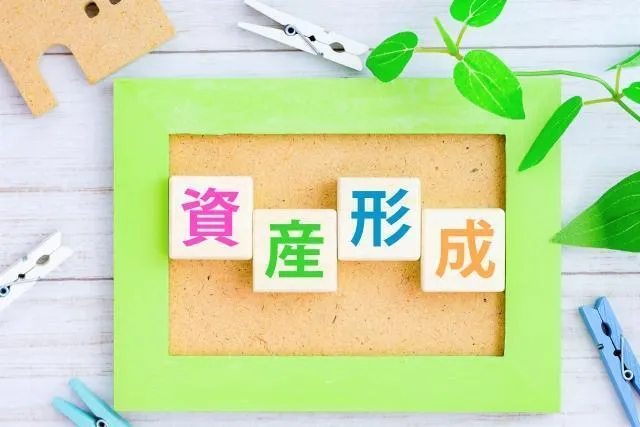
公務員が将来への備えとしてできる方法は、保険だけに限りません。資産形成やリスク分散の観点から、保険以外の選択肢を検討することも重要です。
代表的な方法として、以下の4つが挙げられます。
- 不動産投資
- 団体信用生命保険
- 株式投資
- 確定拠出年金(iDeCo)
それぞれの特徴やメリット・デメリットをみていきましょう。
不動産投資
不動産投資とは、マンションやアパートなどを購入し、賃貸に出して家賃収入を得ることで資産を増やしていく投資方法です。不動産投資のメリット・デメリットは、以下のとおりです。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| ● 安定収入が期待できる ● インフレに強い | ● 空室リスクがある ● 維持管理費がかかる |
長期的に安定した収入が見込めるだけでなく、不動産は物価上昇に強いためインフレ対策としても有効とされています。
また、公務員は社会的信用が高いためローン審査にも通りやすく、不動産投資との相性が良いといわれています。ただし、運用規模などによっては副業にあたる可能性もあるため、収入や保有物件数の管理には注意が必要です。
団体信用生命保険
団体信用生命保険(団信)とは、住宅ローンや不動産投資ローンの契約者が死亡または高度障害になった場合に、ローン残高が保険金によって完済される仕組みです。
住宅ローン契約時に加入することをイメージする方が多いですが、不動産投資用ローンでも団信に加入するケースが一般的です。団体信用生命保険のメリット・デメリットは、以下のとおりです。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| ● 万一のときローン残高がゼロになる ● 不動産を資産として家族に残せる | ● 返済終了と同時に保障も終了する ● ローン金利が上がる場合がある |
団信に加入することで、万が一の際にも遺族に不動産を残すことが可能です。さらに、近年では死亡保障だけでなく、がんに対応した「がん団信」などの保障内容が充実したタイプも選べるようになっています。
このように団信は、不動産投資を通じて「保険」としての役割と「資産形成」の役割を同時に果たす手段として注目されています。
株式投資
株式投資とは企業の株を購入し、その値上がり益や配当金によって利益を得る投資方法です。公務員の場合でも、株式投資は副業禁止規定の対象外とされており、業務に支障のない範囲であれば自由に行うことができます。株式投資のメリット・デメリットは、以下のとおりです。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| ● 値上がり益が狙える ● 配当金が受け取れる | ● 元本割れのリスクがある ● 倒産リスクがある |
また株式投資を始める際は、利益が非課税となる「NISA(少額投資非課税制度)」の活用がおすすめです。2024年から新NISA制度もスタートし、より使いやすくなっています。
ただし、株式投資には株価の変動や倒産による損失リスクもあるため、投資初心者の方は投資信託から始めるのがおすすめです。
確定拠出年金(iDeCo)
確定拠出年金とは、加入者自身が毎月の掛金を拠出し、自分で運用方法を選択して将来の年金原資を積み立てていく制度です。
公務員も2017年からiDeCoの加入が可能となり、さらに2024年12月から拠出限度額が月1万2,000円から2万円に引き上げられました。確定拠出年金のメリット・デメリットは、以下のとおりです。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| ● 掛金が所得控除の対象 ● 運用益も非課税 | ● 原則60歳まで引き出せない ● 元本割れのリスクがある |
iDeCoのメリットは、掛金が所得控除の対象となり、所得税や住民税の節税が期待できる点です。また運用益も非課税となるほか、将来受け取る際にも税制優遇が受けられます。ただし、原則として60歳までは引き出せないため、余剰資金で行うことが重要です。
【国家・地方】公務員の退職金は2200万前後!計算方法と運用についても解説
もぜひチェックしてみてください!
毎年多くのお客様がトーシンパートナーズでマンション経営をスタートしています
月々1万円でローリスク&ロングリターンな資産運用

将来に漠然とした不安を抱えてはいるものの、なにをしたらよいかわからない……。
トーシンパートナーズではそんなお悩みを抱えるみなさまに、マンション経営をご案内しています。
マンション経営と聞くと空室の発生や、家賃の下落・滞納・資産価値の下落などの不安要素が思い浮かぶかもしれません。ですがパートナーとなる会社次第で、ご不安は限りなくゼロに近づけることができます。
家族のために、自分のために、未来の安心のために、ローリスク&ロングリターンな資産運用を始めてみませんか?
Amazonギフト券
プレゼント限定キャンペーン
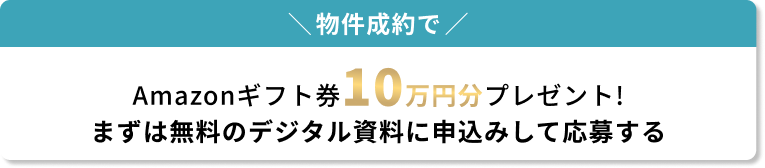
プレゼント適用条件はこちら
≪特典付与の条件≫
- ■キャンペーン名
- 不動産投資マンションご成約でAmazonギフトプレゼントキャンペーン
- ■キャンペーン概要
- トーシンパートナーズで不動産投資マンションをご成約いただいた方へ、もれなく10万分のAmazonギフトをプレゼント。
- ■キャンペーン対象期間
- 2025年11月5日~2026年2月28日
- ■キャンペーン対象条件
- 以下のすべての条件に該当する方
- 2026年2月28日までに資料請求、2026年3月31日までにご購入された方。
- 専用フォームからお申し込みいただいた方
※その他の方法でお申し込みの方は対象外です。 - キャンペーン期間中に初めてトーシンパートナーズで不動産投資マンションをご成約いただいた方。
- ■注意事項
- 本キャンペーンはトーシンパートナーズによる提供です。
- Amazonギフトのお受け取りは、お一人様1回限り10万円です。
- Amazonギフトは、物件購入のお申込みいただき、決済完了後の1か月以内にシリアルコードで送付予定となります。
- 本キャンペーンについてのお問い合わせはAmazonではお受けしておりません。
トーシンパートナーズマーケティング事務局【support@tohshin.co.jp】までお願いいたします。 - Amazon、Amazon.co.jpおよびそれらのロゴはAmazon.com,Inc.またはその関連会社の商標です。
まとめ
公務員は社会保障が充実しているため「保険は不要」といわれることもあります。しかし、実際には公的保障だけではカバーしきれない費用もあるため、複数の保険で幅広いリスクに備える必要があります。
また保険だけでなく、資産形成などによる将来の備えを進めることも重要です。中でも不動産投資は、中長期的な目線で安定収入が見込める有効な選択肢です。
トーシンパートナーズでは、東京都心を中心に自社開発した投資用区分マンションを取り扱っており、月1万円程度から始められるプランもあります。資産価値や空室リスクを考慮した運用が可能なため、老後資金づくりの選択肢としてもおすすめです。