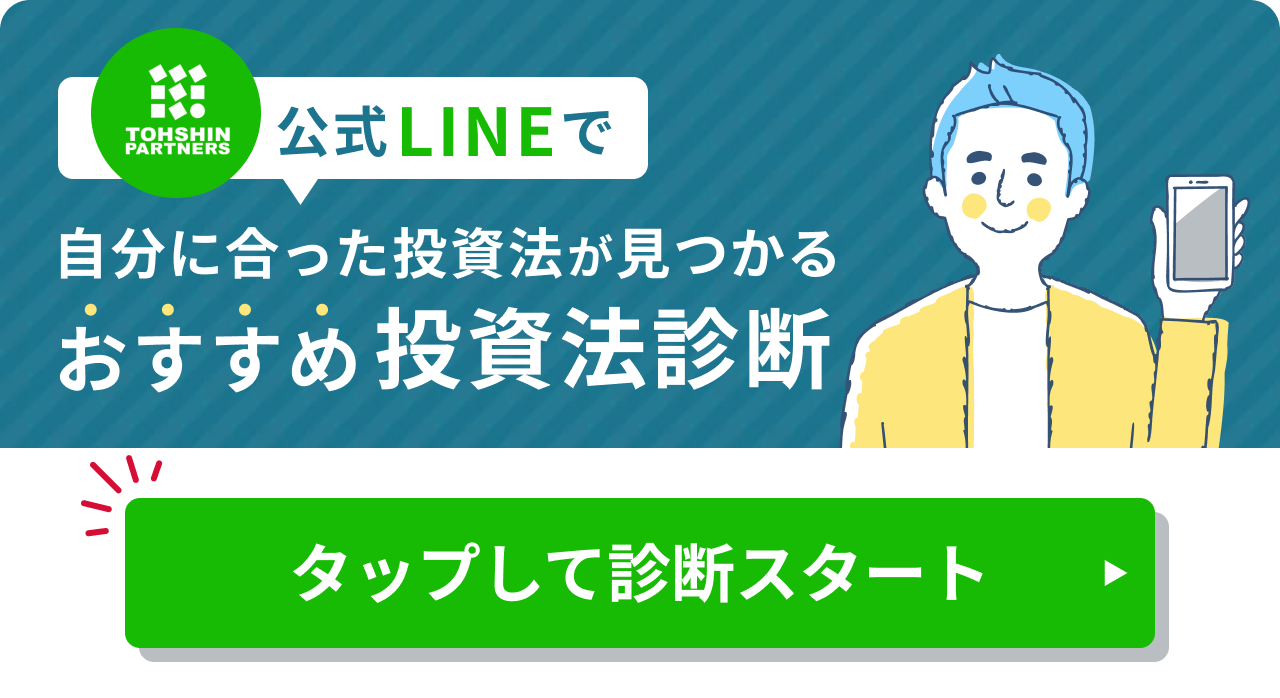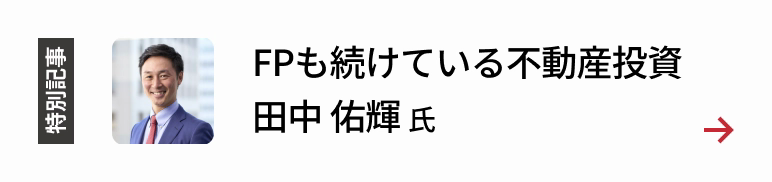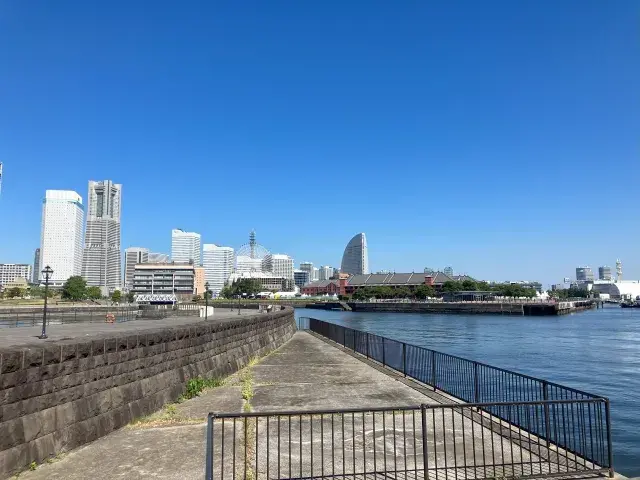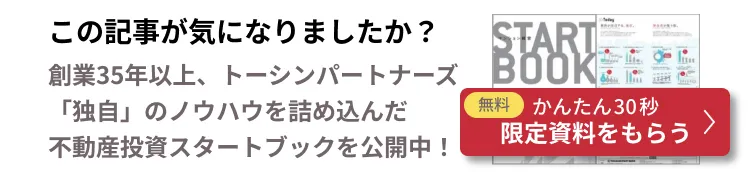- 不動産投資の基礎知識
【保存版】不動産投資で物件売却にかかる4つの税金!計算方法や使える控除も紹介

不動産投資で物件を売却する際に「どのくらい税金がかかるのか」といった疑問を持つ方は多いのではないでしょうか。売却によって得た利益にはさまざまな税金がかかり、物件の所有期間や売却益などによっては大きな負担となることもあります。
この記事では、不動産投資の物件売却時にかかる4つの税金を解説します。計算方法や節税につながる特例制度も紹介しているので、不動産の売却を検討中の方や税金面に不安を抱えている方は、ぜひ参考にしてください。
不動産投資で物件売却の際に発生する4つの税金

不動産投資で物件を売却すると、以下の4つの税金が発生します。
- 譲渡所得税
- 印紙税
- 登録免許税
- 消費税
売却益に対する税や契約・登記時に必要な税など種類が複数あるため、内容を把握しておくことが大切です。全体像を理解しておくことで、納税の準備や資金計画が立てやすくなります。ここでは、不動産投資で物件売却の際に発生する税金について解説します。
譲渡所得税
不動産投資で物件を売却すると、売却益に対して譲渡所得税がかかります。譲渡所得税は、以下3つの税金を合算したもので、確定申告を行ったうえで納付します。
- 所得税
- 住民税
- 復興特別所得税
課税対象となるのは、売却価格から取得費と譲渡費用を差し引いた金額です。また税率は所有期間によって異なり、5年以下なら「所得税30%+住民税9%+復興特別所得税0.63%」の合計39.63%、5年超であれば「所得税15%+住民税5%+復興特別所得税0.315%」の合計20.315%が適用されます。所有していた期間による税率の差が大きいため、売却の時期を意識するだけでも負担を抑えやすくなります。納税漏れや申告ミスを防ぐためにも、譲渡所得税の制度や計算ルールを正しく理解しておきましょう。
印紙税
不動産投資で物件を売却する際には、売買契約書に対して印紙税がかかります。印紙税とは、契約書などの文書に対して課税される税金で、売買金額に応じて定められています。例えば、1,000万円超〜5,000万円以下の契約書には1万円の印紙が必要です。契約書に印紙を貼り付ける方法により納税を行います。
ただし、電子契約を利用すれば印紙税が非課税となるため、コスト削減ができるメリットがあります。なお、印紙税の負担は、契約書の原本を保管する当事者が、その印紙代を負担するのが一般的です。印紙税の納付を忘れると、追徴課税の対象となることがあるため注意しましょう。
登録免許税
不動産売却では、所有権移転登記にともない登録免許税が発生します。原則として買主が負担しますが、贈与や相続が絡む場合は売主側にも納税義務が発生するケースがあるため注意が必要です。税額は、物件の固定資産税評価額に原則2.0%の税率をかけて算出されます。
ただし住宅用の一定条件を満たす物件や、個人間売買などでは軽減税率が適用され、税率が1.5%になる場合もあります。登記手続きは司法書士に依頼するのが一般的で、手続き費用と合わせて把握しておくことが必要です。売却時の資金計画を立てる際には、登録免許税の負担も忘れずに見積もっておきましょう。
消費税
不動産の売却時には、建物部分に対して消費税がかかる場合があります。土地は非課税ですが、建物が課税対象となるのが一般的です。個人が自身の居住用として使っていた物件を売却する場合、原則として消費税は課税されません。一方で、事業用物件や法人名義の売却では、売主が課税事業者に該当する場合に限り、消費税が発生します。
また、売却価格に消費税が含まれているかは、税務上の解釈や請求に関してトラブルにつながることもあるため、取引の初期段階で確認しておくことが重要です。取引条件によっては、納税義務の有無や金額が大きく変わるため、事前に消費税が含まれるか確認しましょう。特に法人や事業として不動産投資を行っている方は、税務処理について税理士や司法書士に相談しておくのがおすすめです。
不動産投資で物件売却時にかかる税金の計算方法

不動産を売却した際に発生する税金は、譲渡所得や所有期間、適用できる控除によって変動します。税額の計算方法や税率の違いなどを理解しておくことで、納税のタイミングや資金準備にも余裕が生まれるでしょう。ここからは、税額の算出方法について具体的な計算の流れを解説します。
譲渡所得の計算方法
不動産を売却して得た利益は「譲渡所得」として扱われ、税額を算出するうえで基本となる金額です。譲渡所得は、売却価格から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。取得費には物件の購入費用のほか、仲介手数料や登記費用などが含まれます。譲渡費用には、売却時に発生する以下のような費用も含まれます。
- 仲介手数料
- 測量費
- 建物の解体費
契約書や領収書を紛失している場合は、売却価格の5%を取得費とみなす「概算取得費」で計算することも可能です。費用の内訳を正確に把握しておくことで、譲渡所得を適切に算出し、スムーズな納税準備へとつながります。
税率の計算方法
譲渡所得に対する税率は、5年以下の短期所有であれば約39%、5年を超える長期所有なら約20%が適用されます。この税率は、以下3つの税金を合算して算出されます。
- 所得税
- 住民税
- 復興特別所得税
所有期間の判定は、売却年の1月1日時点で5年を超えているかが基準です。例えば、2019年2月に取得した不動産を2025年6月に売却する場合でも、2025年1月1日時点では5年未満と見なされるため、短期譲渡として扱われます。
税額は「譲渡所得×税率」で求められ、確定申告を行ったうえで納付する流れです。所有期間の違いで課税額に大きな差が出るため、売却の際に確認することをおすすめします。
控除を反映した計算方法
譲渡所得には、条件を満たすことで税負担を軽減できる控除制度がいくつかあります。代表的なのが、自宅を売却した際に適用できる「3,000万円特別控除」です。
また、同じく居住用財産を一定期間以上保有していた場合には、長期譲渡所得に対して軽減税率が適用される「居住用財産の特例」もあります。一方で、売却によって損失が出た場合には、その損失を他の所得と相殺したり、翌年以降に繰り越して適用したりできる「譲渡損失の繰越控除」も活用できます。
これらの控除制度には、居住年数や売却先との関係など、それぞれ適用要件が設けられており、確定申告での申請が必要です。事前に内容を確認し、適用の可否を判断しておくことで、納税に必要な資金や手続きを把握できます。
不動産投資で物件売却時の税金に関する3つの注意点

不動産投資における売却時には、税金に関する正しい知識が必要です。譲渡所得の税率は所有期間によって変わり、減価償却の影響で課税額が増える場合もあります。
さらに、申告時のミスによって追加の税負担が生じる可能性もあるため、注意点を事前に把握しておきましょう。ここでは、特に押さえておきたい物件売却時の税金に関する3つのポイントを解説します。
所有期間による課税額の違い
不動産の所有期間が5年を超えるかどうかで、売却時の税率に大きな差が生じます。具体的には、5年以下の「短期譲渡所得」では約39%、5年超の「長期譲渡所得」では約20%が課税されます。この違いは税負担に直結するため、できる限り納税額を抑えたい場合は、売却のタイミングを意識しておくといいでしょう。
所有期間は、物件を実際に取得した日から、売却した年の1月1日時点で5年を超えているかで判断されます。例えば2019年12月に取得した物件を2025年2月に売却した場合、2025年1月1日時点で5年に満たないため、短期譲渡として扱われます。
短期と長期の税率差は大きく、売却益が大きい場合には数十万円以上の差が出ることもあります。税負担を軽減するためには、事前に所有期間を確認し、計画的に売却時期を検討することが求められます。
減価償却による課税所得の増加
不動産を賃貸運用していた場合、減価償却費を計上することで毎年の所得税を軽減できます。ただし、売却時にはこの減価償却費が「取得費」から差し引かれるため、結果的に譲渡所得が増加する可能性があります。
帳簿上の取得費が少なくなるほど課税対象が大きくなり、納税額も想定より膨らむ恐れがあるため注意が必要です。例えば、長期保有で減価償却費が累積している場合、売却益が少なくても多額の税金が発生するケースもあります。売却を検討する段階で、減価償却の累計額を確認しておくと安心です。
申告漏れや過少申告によるペナルティ
不動産売却によって得た譲渡所得は、原則として確定申告が必要です。ただし譲渡益が「3,000万円特別控除」などの適用によって全額非課税となり、かつ税金の還付も発生しない場合には、確定申告が不要とされるケースもあります。
申告を忘れたり、金額を少なく申告したりした場合には、延滞税や過少申告加算税が課されます。特に悪質と判断されると、重加算税として最大で本来の税額の35〜40%が追加されるケースがあるため注意が必要です。
実際には、書類の不備や制度の誤解によってミスが生じることがあります。税務調査で発覚すると、追徴課税に加えて、是正のための時間や手間がかかります。不明点があるときは、税務署に確認したり税理士に相談したりすることで、トラブルを回避できる可能性が高くなるでしょう。
不動産投資で物件売却時に活用できる税金の特例と税制優遇制度

不動産投資で物件を売却すると、利益に応じた税金が発生しますが、一定の条件を満たすことで適用できる特例や税制優遇制度があります。これらの制度を活用すれば、最終的な納税額を大きく抑えられる可能性が高いです。ここでは、物件売却時に活用できる税金の特例と税制優遇制度について解説します。
長期譲渡所得の軽減税率
所有期間が5年を超える不動産を売却した場合、長期譲渡所得として約20%の軽減税率が適用されます。短期譲渡の約39%と比べて税負担が大きく下がるため、老後資金の確保や住み替えを目的に売却を検討しているケースでは、所有期間を確認したうえで売却時期を検討することで節税効果が期待できるでしょう。
長期譲渡所得の税率は、所得税・住民税・復興特別所得税の合算によって構成されます。所有期間の計算方法には注意が必要になり、売却する年の1月1日時点で5年を超えているかが基準となります。
例えば、2019年2月に取得した物件を2025年2月に売却した場合でも、2025年1月1日時点では5年に達していないため、短期譲渡の税率が適用されます。わずかなタイミングの差で税率が変わるため、売却時期の見極めはとても重要です。将来的な売却を想定している場合は、5年の判定基準を意識しておきましょう。
譲渡損失の繰越控除
不動産を売却した際に譲渡損失が発生しても、一定の条件を満たせば節税につなげられます。この場合に利用できるのが「譲渡損失の繰越控除」という制度です。譲渡損失とは、売却価格よりも取得費や譲渡費用が上回ったときに発生する赤字を指します。
譲渡損失は給与所得や事業所得などの他の所得と損益通算でき、さらに控除しきれなかった分は翌年以降に繰り越すことも認められています。繰越可能な期間は最長3年間で、毎年の確定申告が必要です。
なお、住宅ローンが残っている物件を売却する場合には、損益通算に加えて、別途要件の確認も求められます。売却による利益が出なかった場合でも、譲渡損失の繰越控除を適切に活用することで税負担を軽減できる可能性があります。
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例
以前に自宅として使用していた不動産を売却する際は「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」が適用される可能性が高いです。たとえ現在は投資用物件として運用していても、過去に自身が居住していた実績があり、一定の条件を満たす場合には対象となるケースがあります。
主な適用条件としては、以下のようなものが挙げられます。
- 自分が住んでいた住宅であること
- 住まなくなってから3年目の12月31日までに売却すること
- 同一の控除を同一年内で重複して利用していないこと
売却益が大きい場合でも「3,000万円の特別控除」が適用できれば、課税される譲渡所得の金額を大幅に抑えられるため、活用できるかを確認しておくことが大切です。また、この制度は確定申告を行わなければ適用されません。必要書類を整理し、条件に合致しているかを不動産会社や税理士に相談しておきましょう。
毎年多くのお客様がトーシンパートナーズでマンション経営をスタートしています
月々1万円でローリスク&ロングリターンな資産運用

不動産投資では、物件を売却する際に「税金はいくらかかるのか」「いつ納税することになるのか」といった不安を感じる方が多いのではないでしょうか。実際、税額は売却益の金額だけでなく、所有期間や控除の有無によっても大きく変わるため、事前の理解と準備が大切です。
税制を正しく理解し、適切な対策を講じておくことで、手元に残る資金を最大化できる可能性があります。売却益を次の資産形成につなげるためにも、税金面でのポイントを押さえておきましょう。不安なく手続きを進めるためには、税務や運用の知識を持つパートナーに相談しながら進めるのも有効です。
月々1万円から始められるプランもあり、無理のない範囲で未来への備えが可能です。家族の安心、自分自身の将来のために、ローリスク&ロングリターンを目指せる資産形成を検討してみてはいかがでしょうか。
Amazonギフト券
プレゼント限定キャンペーン
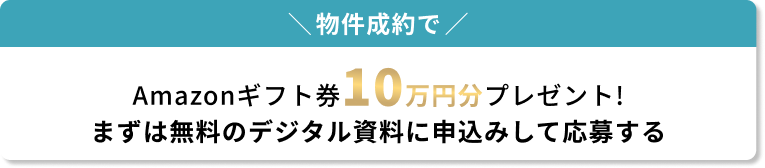
プレゼント適用条件はこちら
≪特典付与の条件≫
- ■キャンペーン名
- 不動産投資マンションご成約でAmazonギフトプレゼントキャンペーン
- ■キャンペーン概要
- トーシンパートナーズで不動産投資マンションをご成約いただいた方へ、もれなく10万分のAmazonギフトをプレゼント。
- ■キャンペーン対象期間
- 2025年11月5日~2026年2月28日
- ■キャンペーン対象条件
- 以下のすべての条件に該当する方
- 2026年2月28日までに資料請求、2026年3月31日までにご購入された方。
- 専用フォームからお申し込みいただいた方
※その他の方法でお申し込みの方は対象外です。 - キャンペーン期間中に初めてトーシンパートナーズで不動産投資マンションをご成約いただいた方。
- ■注意事項
- 本キャンペーンはトーシンパートナーズによる提供です。
- Amazonギフトのお受け取りは、お一人様1回限り10万円です。
- Amazonギフトは、物件購入のお申込みいただき、決済完了後の1か月以内にシリアルコードで送付予定となります。
- 本キャンペーンについてのお問い合わせはAmazonではお受けしておりません。
トーシンパートナーズマーケティング事務局【support@tohshin.co.jp】までお願いいたします。 - Amazon、Amazon.co.jpおよびそれらのロゴはAmazon.com,Inc.またはその関連会社の商標です。
まとめ

不動産投資の売却では、譲渡所得税(所得税・住民税・復興特別所得税の総称)や印紙税など、複数の税金が関係します。所有期間や減価償却の状況によって税額が大きく変わるため、あらかじめ仕組みを理解し、必要な知識を整理しておくことが重要です。確定申告や特例制度を正しく活用できれば、納税額を抑えることも可能になります。
売却時期の判断には専門的な知識が求められるため、信頼できるパートナーの存在が重要です。税制上における特例の適用条件や計算方法に不安がある方は、トーシンパートナーズへご相談ください。プロの担当者が丁寧にサポートし、物件の購入から物件の売却に至るまで、納得のいく不動産投資を一緒に実現いたします。