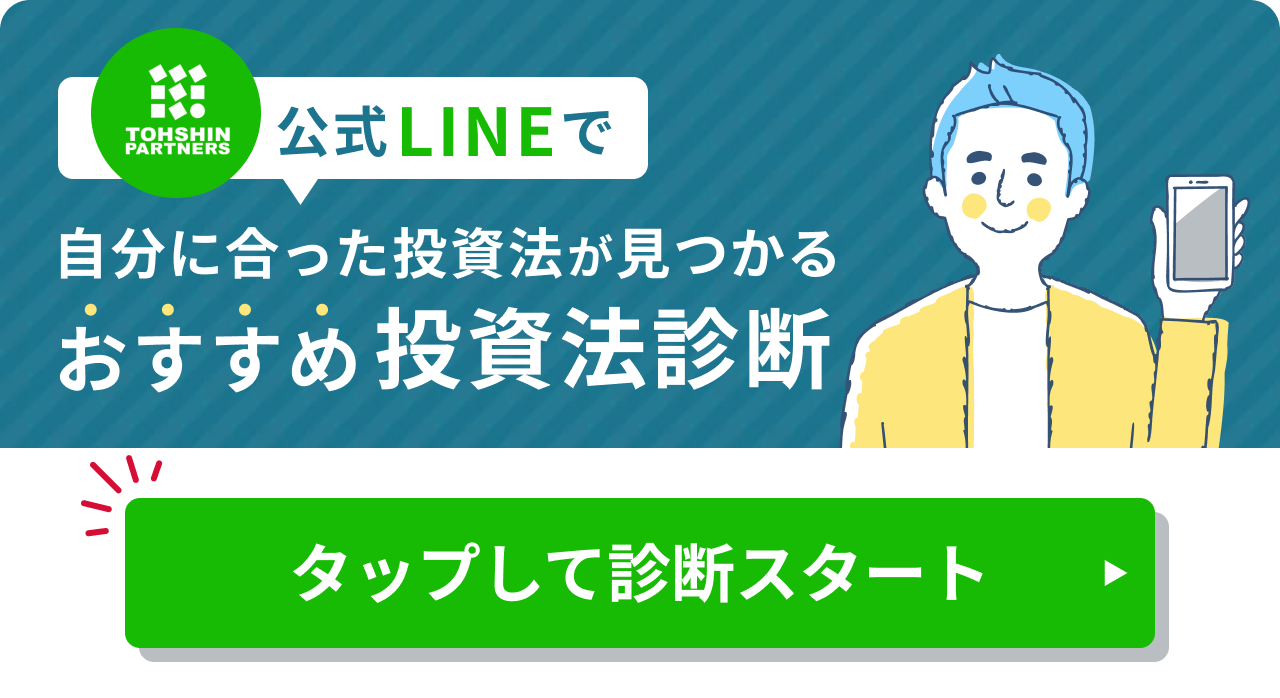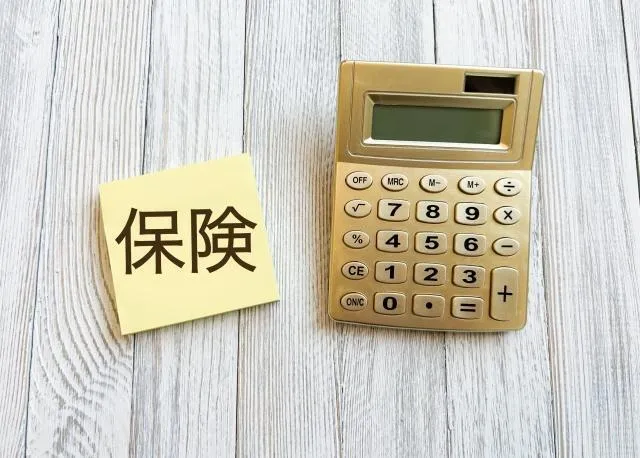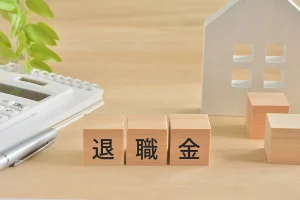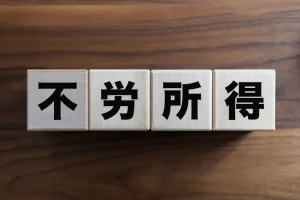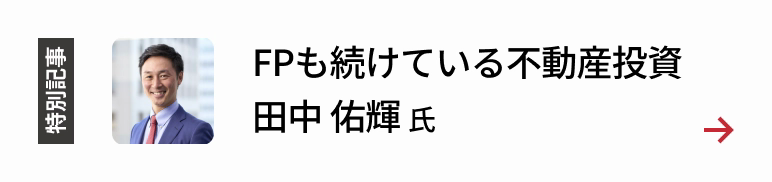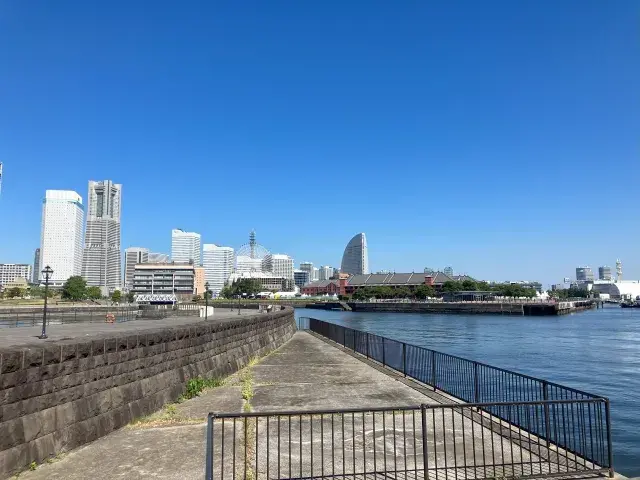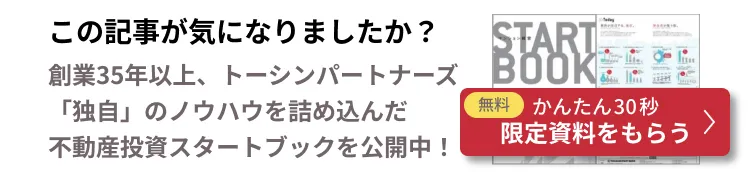- 不動産投資の基礎知識
【国家・地方】公務員の退職金は2200万前後!計算方法と運用についても解説

公務員として働いている方のなかには「自分はどのくらい退職金をもらえるのだろう」「退職金だけで老後の生活費をまかなえるのか」と不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
公務員にはあらかじめ退職金の計算方法が定められており、勤務年数や退職時の俸給月額によって、ある程度の支給額を把握できます。
この記事では、国家公務員・地方公務員それぞれの退職金の平均額や計算方法について解説します。
公務員の退職金は国家公務員と地方公務員で異なる

多くの企業では、退職の際に退職金が支給されます。それと同様に、公務員も退職時には一定額の退職金を受け取ることが可能です。
ただし、公務員といっても「国家公務員」と「地方公務員」とでは、退職金の支給額に違いが生じます。ここでは、それぞれの退職金の平均額について解説します。
国家公務員の退職金の平均
内閣官房内閣人事局が公表した資料によると、2023年度中に退職した国家公務員の退職金は以下のとおりです。
- 全体の退職金平均額(定年退職以外も含む):約910万円
- 定年退職した場合の平均退職金額:約2,150万円
2022年度の民間企業における定年退職金の平均額は、大手企業の大学卒で2,139万6,000円となっており、国家公務員の定年退職金とほぼ同水準です。このことからも、国家公務員の退職金は大手企業と比較しても遜色のない水準にあるといえるでしょう。
地方公務員の退職金の平均
総務省が公表した「令和6年地方公務員給与実態調査」によると、2023年4月1日から2024年3月31日までに退職した地方公務員の退職金額は以下のとおりです。
- 全体の退職金平均額:920万6,000円
- 定年退職した場合の平均退職金額:約2,270万円
このように、データ上では国家公務員よりも地方公務員の退職金の方がやや高い傾向にあることがわかります。また国家・地方を問わず、定年まで勤め上げた場合はいずれも2,000万円を超える水準となっています。
退職金運用の失敗談|よくある失敗例や「成功」の考え方・ポイントを解説
もぜひチェックしてみてください!
公務員の退職金は減少傾向にある

公務員の退職金は安定しているイメージがありますが、実際には15年前の退職金と比較すると減少傾向にあります。地方公務員の定年退職金の平均額を時系列で確認すると、その推移がわかります。
以下の表は、2008年から2023年までの地方公務員の定年退職金の平均額をまとめたものです。
| 年度 | 退職金の平均 |
|---|---|
| 2008年(平成20年) | 2778万円 |
| 2009年(平成21年) | 2754万円 |
| 2010年(平成22年) | 2735万円 |
| 2011年(平成23年) | 2722万円 |
| 2012年(平成24年) | 2716万円 |
| 2013年(平成25年) | 2648万円 |
| 2014年(平成26年) | 2456万円 |
| 2015年(平成27年) | 2328万円 |
| 2016年(平成28年) | 2295万円 |
| 2017年(平成29年) | 2296万円 |
| 2018年(平成30年) | 2218万円 |
| 2019年(平成31年) | 2213万円 |
| 2020年(令和2年) | 2211万円 |
| 2021年(令和3年) | 2209万円 |
| 2022年(令和4年) | 2204万円 |
| 2023年(令和5年) | 2199万円 |
このように、2008年には2,778万円だった平均退職金が、2023年には2,199万円まで下がっており、15年間で約600万円もの減少が見られます。退職金がこれほど縮小している現状では、退職金だけに頼らない老後資金の準備が必要になるといえるでしょう。
公務員の退職金が支給される仕組み

退職金は誰でも一律でもらえるものではなく、一定の勤務年数や条件を満たす必要があります。ここでは公務員の「支給対象となる勤務年数」と「支給のタイミング」について詳しく解説します。
支給対象となる勤務年数
公務員の退職金は、原則として勤続年数が1年以上あれば支給される仕組みです。たとえば国家公務員の場合、在職期間が1年に満たない場合は切り捨てとなり、退職金の支給対象外になります。
一方で地方公務員については、各自治体の条例によって取り扱いが異なる点に注意が必要です。たとえば「6か月未満は切り捨て」「6か月以上は切り上げ」といった基準が設けられているケースもあります。
ただし勤続年数が1年以上あっても、以下のいずれかに該当する場合は退職金が支給されないことがあります。
- 懲戒免職処分を受けた場合
- 禁錮以上の刑に処されるなどして失職となった場合
- 同盟罷業(ストライキ)などにより懲戒退職となった場合
このように、公務員の退職金は一定の勤務年数を満たしていれば支給される一方で、退職理由によっては不支給となるケースがあることも理解しておきましょう。
支給のタイミング
公務員の退職金は、退職後すぐに支給されるわけではなく、通常は退職した翌月中に振り込まれることになります。
たとえば、以下のようなスケジュールが一般的です。
- 10月退職:11月中に支給
- 2月退職:3月中に支給
このように、退職した月の翌月に振り込まれるのが基本的なルールとなります。なお、国家公務員の退職金の支給時期は「国家公務員退職手当法」によって明確に定められており、地方公務員についても原則として同様の取り扱いがなされています。
退職金の計算方法をシミュレーション
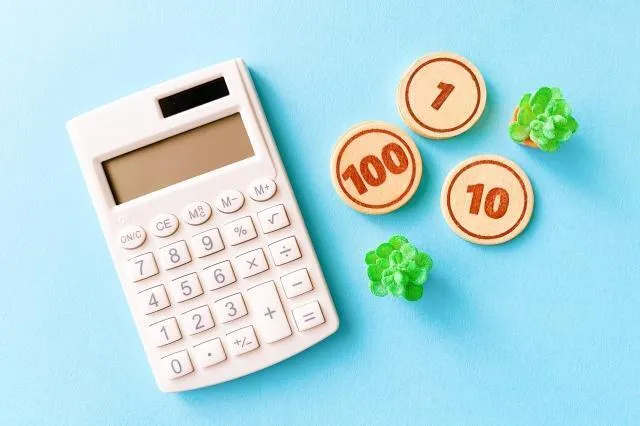
ここでは、公務員が受け取る退職金について、具体的な計算方法とシミュレーションを解説します。
退職手当の支給額の計算方法
国家公務員・地方公務員ともに、退職金の計算方法は共通しています。具体的な支給額は、以下の式で算出されます。
| 退職金=基本額+調整額 |
基本額:退職日の俸給月額×退職理由別・勤続期間別の支給率
調整額:在職期間中の勤務成績や貢献度に応じた加算額
退職理由別・勤続期間別の支給率は、法令で定められた基準に調整率をかけたものです。調整額については、退職手当の調整額区分表に基づき、あらかじめ定められた単価に最大60か月分を乗じて支給されます。この加算は、勤務年数や退職理由などによっても異なるため、個別に確認が必要です。
このように、公務員の退職金は単に勤続年数だけでなく、退職理由や在職中の評価なども加味されて計算されるのが特徴です。
退職金は課税対象となる
公務員の退職金にも所得税と住民税がかかります。ただし、その計算方法は給与などの所得とは異なります。
退職金を一時金として受け取る場合は「退職所得控除」を差し引いたうえで、退職金だけを切り離して税額を計算する仕組みです。そのため、他の所得と比べて税金の負担が軽くなるよう配慮されています。
具体的な退職所得の計算式は以下のとおりです
| (退職金−退職所得控除額)×1/2(1,000円未満切り捨て) |
退職所得控除の求め方は以下のとおりです。
| ・勤続年数が20年以下の場合:勤続年数×40万円(80万円未満の場合は80万円) ・勤続年数が20年を超える場合:800万円+70万円×(勤続年数-20年) |
たとえば、退職金が2,000万円、勤続年数が35年の方の場合で退職所得控除を算出してみます。
| 退職所得控除額=800万円+70万円×(35年−20年) =1,850万円 課税対象所得=(2,000万円−1,850万円)×1/2 =75万円 |
この75万円が課税所得となり、そこから税額が計算されます。退職金に関しては勤務先で「退職所得の受給に関する申告書」を提出しておけば、源泉徴収で課税関係が完結するため、原則として確定申告は不要です。
公務員で30年勤めた場合の退職金シミュレーション
実際に公務員が30年間勤務した場合の退職金がどの程度になるのか、以下の条件でシミュレーションしてみましょう。
- 在職期間:30年
- 退職事由:定年退職
- 最終俸給月額:37万5,300円
- 退職理由別・勤続期間別の支給率:40.80375
- 調整額(月額):3万2,500円×60か月分
この条件をもとに退職金を計算すると、以下のようになります。
| 基本額:37万5,300円×40.80375=1,531万3,647円 調整額:3万2,500円×60か月=195万円 合計退職金:1,531万3,647円+195万円=1,726万3,647円 |
このように、30年間勤め上げた場合には1,700万円を超える退職金が見込める計算になります。ただし、実際の金額は職務の等級や役職、評価などによって異なる点には注意が必要です。
退職金の運用におすすめの方法8選!運用のコツや取り崩し方まで要チェック
もぜひチェックしてみてください!
退職金だけでは老後生活が不足するケースがある

公務員を定年退職した際には、平均しておおむね2,000万円程度の退職金が支給されることがわかりました。しかし、退職金2,000万円で老後生活のすべてをまかなえるかどうか不安に感じる方も多いでしょう。
一般的に、老後に必要な資金は2,000〜3,000万円といわれています。
2019年に金融庁が公表した報告書(市場ワーキング・グループ)によると、65歳以上の夫婦世帯は毎月約5万円が不足し、老後30年で約2,000万円の資金が足りなくなると指摘されています。
もし、旅行や趣味も楽しむような「ゆとりある老後」を目指す場合、月の生活費は約38万円にのぼるとされており、必要な老後資金は6,000万円前後になることもあります。さらに近年の物価高騰を踏まえると、将来的にはさらに多くの資金が必要になる可能性もあるでしょう。
こうした背景から、退職金だけに頼っていると、老後生活の途中で資金が枯渇するリスクがあります。
退職金に不安がある公務員におすすめな老後資金の準備方法
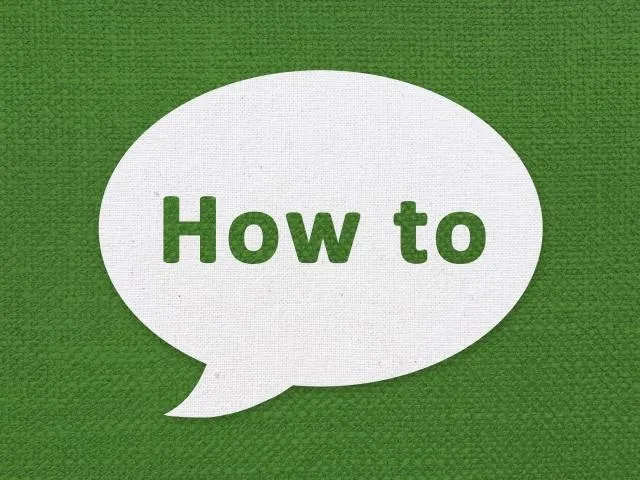
ここでは、公務員におすすめの老後資金の準備方法について紹介します。主な準備方法は、以下の4つです。
- NISA
- 個人年金保険
- iDeCo
- 不動産投資
それぞれの特徴について、詳しくみていきましょう。
NISA
NISAとは、専用の口座を利用して投資を行うことで、運用益や配当金にかかる税金が非課税となる制度です。通常、株式や投資信託の売却益や配当には約20%の税金がかかりますが、NISAを活用すれば非課税扱いとなり利益をそのまま受け取れます。
NISAを活用するメリット・デメリットは、以下のとおりです。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| ● 運用益や配当が非課税になる ● 少額(100円~)で積立可能 | ● 投資対象が限定されている ● 元本割れのリスクがある ● 非課税枠に上限がある |
NISAでは積立型の投資信託が利用できるため、事前に設定した銘柄・金額・購入日に基づき自動で投資を行うことができます。また少額から積み立てられるため、投資経験の浅い方でも気軽に始められるのが魅力です。
ただし、NISAで扱う商品は元本が保証されておらず、市場状況によっては元本割れを起こしてしまう可能性がある点に注意が必要です。
個人年金保険
個人年金保険は、将来の年金受取を目的として、毎月保険料を積み立てる仕組みの保険です。一定期間積み立てた後、契約時に決めた年齢になると年金形式で保険金を受け取ることができます。
個人年金保険を活用するメリット・デメリットは、以下のとおりです。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| ● 計画的に老後資金を準備できる ● 保険料控除で税金の軽減が期待できる | ● 中途解約時の返戻率が低いことがある ● 途中での見直しが難しい場合がある |
個人年金保険は満期後に定額の年金が受け取れるため、計画的に老後資金を準備したい方に向いています。また保険料控除の対象となるため、所得税や住民税の節税効果もあります。
一方で契約して早い段階で解約してしまうと、掛金よりも少ない解約返戻金しか戻ってこない可能性が高い点に注意しましょう。
iDeCo
iDeCo(個人型確定拠出年金)とは、自分で積み立てて運用し、60歳以降に年金または一時金として受け取る私的年金制度です。老後の備えとして、公的年金にプラスして準備したい方に向いています。
iDeCoを活用するメリット・デメリットは、以下のとおりです。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| ● 掛金が全額所得控除となり節税効果が高い ● 自分で運用商品を選べる | ● 原則60歳まで引き出せない ● 手数料がかかる(管理料など) |
iDeCoでは、掛金が全額所得控除の対象となるため、年末調整や確定申告を通じて所得税や住民税の負担を軽減できます。また受け取り時にも税制上の優遇があり、一時金で受け取る場合は「退職所得控除」が、年金形式で受け取る場合は「公的年金等控除」が適用されます。
ただし、原則として60歳まで資金を引き出すことができないため、すぐに使う予定のない余剰資金で始めることが大切です。
不動産投資
不動産投資とは、マンションやアパートなどの不動産を購入して、家賃収入を得ることを目的とした運用方法です。公務員は信用力が高くローン審査に通りやすいため、不動産投資との相性が良いと言われています。
不動産投資を活用するメリット・デメリットは、以下のとおりです。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| ● 家賃収入で安定的な収入が見込める ● 団信により万一の備えにもなる ● インフレに強く資産価値が下がりにくい | ● 空室・修繕などのリスクがある ● 不動産会社選びに注意が必要 |
不動産投資は定年後も安定した家賃収入が得られるだけでなく、ローン契約時には団体信用生命保険に加入するため、万が一の際にも家族に資産を残すことができます。さらに、不動産はインフレにも強く、物価上昇局面でも資産価値が目減りしにくい特徴があります。
一方で不動産投資は、物件選びや適切な管理を行うことが重要です。空室リスクを軽減するためにも、信頼できる不動産会社に管理を依頼しましょう。
公務員に保険が不要と言われる理由を解説!制度でカバーできないリスクと対策を紹介
もぜひチェックしてみてください!
毎年多くのお客様がトーシンパートナーズでマンション経営をスタートしています
月々1万円でローリスク&ロングリターンな資産運用

将来に漠然とした不安を抱えてはいるものの、なにをしたらよいかわからない……。
トーシンパートナーズではそんなお悩みを抱えるみなさまに、マンション経営をご案内しています。
マンション経営と聞くと空室の発生や、家賃の下落・滞納・資産価値の下落などの不安要素が思い浮かぶかもしれません。ですがパートナーとなる会社次第で、ご不安は限りなくゼロに近づけることができます。
家族のために、自分のために、未来の安心のために、ローリスク&ロングリターンな資産運用を始めてみませんか?
Amazonギフト券
プレゼント限定キャンペーン
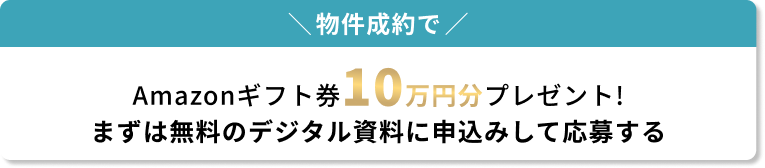
プレゼント適用条件はこちら
≪特典付与の条件≫
- ■キャンペーン名
- 不動産投資マンションご成約でAmazonギフトプレゼントキャンペーン
- ■キャンペーン概要
- トーシンパートナーズで不動産投資マンションをご成約いただいた方へ、もれなく10万分のAmazonギフトをプレゼント。
- ■キャンペーン対象期間
- 2025年11月5日~2026年2月28日
- ■キャンペーン対象条件
- 以下のすべての条件に該当する方
- 2026年2月28日までに資料請求、2026年3月31日までにご購入された方。
- 専用フォームからお申し込みいただいた方
※その他の方法でお申し込みの方は対象外です。 - キャンペーン期間中に初めてトーシンパートナーズで不動産投資マンションをご成約いただいた方。
- ■注意事項
- 本キャンペーンはトーシンパートナーズによる提供です。
- Amazonギフトのお受け取りは、お一人様1回限り10万円です。
- Amazonギフトは、物件購入のお申込みいただき、決済完了後の1か月以内にシリアルコードで送付予定となります。
- 本キャンペーンについてのお問い合わせはAmazonではお受けしておりません。
トーシンパートナーズマーケティング事務局【support@tohshin.co.jp】までお願いいたします。 - Amazon、Amazon.co.jpおよびそれらのロゴはAmazon.com,Inc.またはその関連会社の商標です。
まとめ
国家公務員の平均定年退職金は、約2,150万円、地方公務員は約2,270万円です。一方で、老後に必要な資金は2,000〜3,000万円が目安とされており、最近の物価上昇を考慮すると、その額はさらに増える可能性があります。
そのため、退職金とは別に自身で資産を形成しておくことが重要です。特に公務員の方は信用力が高く、ローン審査にも通りやすいため、不動産投資で資産形成を進めていくことが効果的です。
トーシンパートナーズでは、首都圏の人気エリアを中心に、新築ワンルームマンション等への投資プランをご案内しています。資産価値や空室リスクを抑えた運用を目指せるため、老後資金の準備手段として検討してみてはいかがでしょうか。