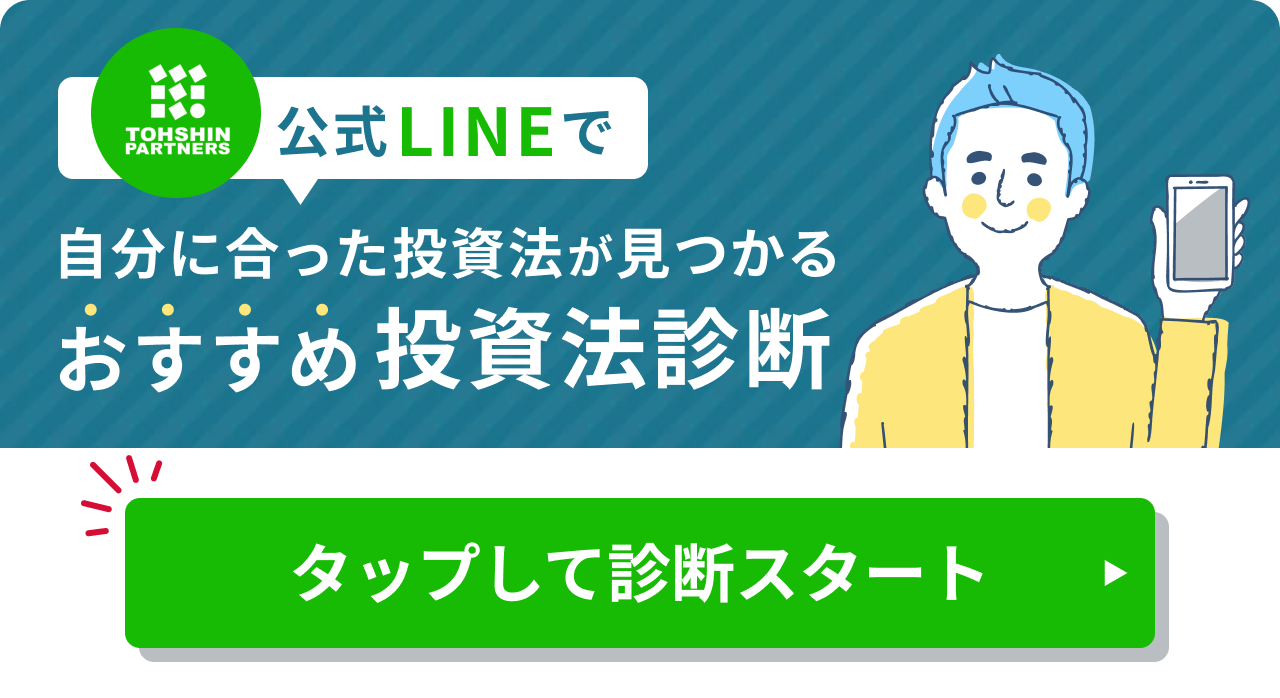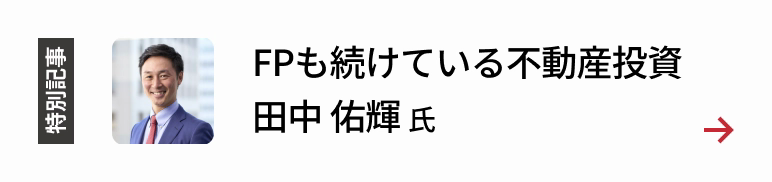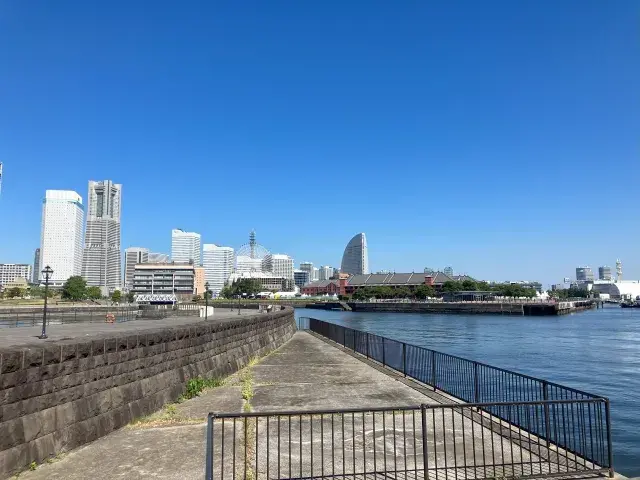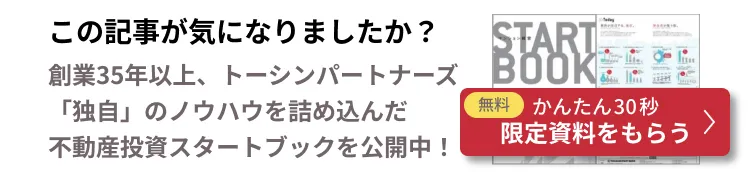- 不動産投資の基礎知識
「もう1つの年金」になるマンション経営|老後も安心できる6つのメリットを解説

定年が近づくと、多くの方が「年金だけで本当に生活できるだろうか」と不安を感じ始めます。厚生労働省の統計によると、平均的な年金受給額は生活費を下回っており、貯蓄を取り崩さなければ家計が成り立たないケースも多いです。物価上昇や医療費の増加も重なり「何かしらのプラス収入を持つこと」が老後の安心につながります。
そこで、マンション経営からの家賃収入で年金を補う方法が注目されています。公的年金と似て継続性があり、自分で資産を形成できる点が魅力です。
本記事では、老後の安心を支えるマンション経営のメリットや注意すべきリスクをわかりやすく解説します。老後資金に不安がある方や、年金以外で収入を見込める方法を模索している方は、ぜひ参考にしてください。
老後は年金だけでは生活費が不足する懸念がある

年金は老後の暮らしを支える制度です。しかし、年齢を重ねると医療費が増加し支出は増える傾向にあり、年金だけに頼る生活はリスクが高いといえるでしょう。ここでは、統計データをもとに、老後の収入と支出の現実を解説します。
年金受給金額の平均は月額147,360円
老後の主な収入源となるのは「年金」ですが、実際の受給額を見ると生活費をまかなうには十分とはいえません。厚生労働省の資料によると、会社員や公務員などが加入する「厚生年金」の平均受給額は月額147,360円、自営業者などが加入する「国民年金」は月額57,700円です。
年金の受け取りは、原則として65歳からです。希望すれば60歳から繰り上げて受給できますが、支給は最大で24%減額されます。過去に国民年金の未納があると、受け取る年金額はさらに少なくなります。繰り上げ受給は短期的には得に見えても、長い老後を考えると慎重な判断が必要です。
現役時代の収入に比べて生活水準が下がることを踏まえると、年金を補う収入源を早めに準備することが重要です。
65歳以上の夫婦のみ世帯で月の支出は256,521円
総務省の家計調査報告によると、65歳以上の無職世帯における1ヶ月平均の収入と支出は以下のとおりです。
| 平均収入 | 平均支出 | |
| 65歳以上の夫婦のみ | 252,818円 | 256,521円 |
| 65歳以上の単身 | 134,116円 | 149,286円 |
収入が不足しており、貯金があっても生活の仕方によっては家計に余裕がない可能性があります。年金受給額と比較すると、月10万円以上足りません。そのため、現役時代と比べて年金生活では外食や旅行の回数を減らすなど、支出を抑える工夫が必要です。しかし、光熱費や医療費のように年齢を重ねるほど増える支出もあり、節約だけで対応するのは現実的ではありません。
平均寿命を考えると退職後の生活は15年以上続く可能性が高く、毎月10万円の不足が続くと総額では2,000万円近い金額を用意しなくてはいけません。老後の家計では、年金だけの収入では月の収支で赤字が生じやすく、生活費を補うための安定した収入源を早めに用意しておくことが大切です。
「もう1つの年金」になり得るマンション経営

年金だけに頼る老後生活では、不安が残ります。そこで注目されているのが、マンション経営によって「自分でつくるもう1つの年金」を持つことです。マンション経営と年金には以下のとおりの共通点があり、どちらも安定した老後の生活を支える継続的な収入源として機能します。
| 共通点 | 年金 | マンション経営 |
| 収入 | 定額を定期的に受給できる | 家賃収入を毎月受け取れる |
| 継続性 | 一生涯受け取れる | 所有している間は収入が続く |
| 安定性 | 景気に左右されない | 景気やインフレに強い |
どちらも時間や労力をあまりかけずに収入を得られ、さらにマンション経営は「自らコントロールできる収入源」です。マンション経営は自分の判断で物件選びや運用を行えるため、より積極的に老後資金を確保できます。定年を迎え給与が途絶えた後も自分でつくる第二の年金として、老後の安心を支える有効な手段といえます。
マンション経営が年金対策になる6つのメリット

「老後の生活費が年金だけでは不安」と感じている方にとっては、マンション経営は悩みを解消できる選択肢の1つです。毎月の家賃収入が安定して入り続けるため、生活費の不足分を補いながら将来の安心につなげられます。ここでは、マンション経営が年金対策としてどのように役立つのか、6つのメリットを解説します。
家賃で安定した収入を得られる
マンション経営は、入居者がいれば毎月決まった日に家賃が振り込まれ、年金と同じく「継続的に得られる収入源」です。公的年金が国から支給されるものに対して、マンション経営では「自分の資産」が生み出す収入です。
家賃は入居者の数や賃料設定によって収入の見通しを立てやすく、老後の生活費の不足分を計画的に補えます。たとえば「毎月10万円の家賃収入を得る」という目標を立てれば、物件を選びやすいです。
しかし、空室が発生すれば一時的に収入が減るリスクがあります。需要のあるエリアを選び、長期的に入居が見込める物件を保有することが重要です。適切に管理すればマンション経営は年金のように安定して得られる収入源となり、老後の経済的な安心を支える強い味方になります。
長期的な不労所得である
マンションは鉄筋コンクリート造の物件が多く、老後も安定して家賃収入を得られます。木造住宅の耐用年数は約22年ですが、鉄筋コンクリート造では約47年です。築20年の中古マンションを購入しても、20年以上の運用継続が期待できるのは大きな安心材料です。
また、マンション経営は比較的少ない労力で収入が得られます。長期的に毎月の家賃収入が見込めるため、退職後や体調を崩して働けない時期でも安心です。物件の管理や入居者対応は管理会社に委託できるため、オーナー自身が細かな対応におわれることはありません。清掃・設備点検・修繕などをプロに任せれば、仕事や家事に追われる現役世代でも無理なく始められます。
家賃収入があっても年金は減らない
年金を受給しながら収入を得ると、年金が減らされると心配される方がいます。しかし、年金の支給が調整されるのは「在職老齢年金制度」と呼ばれる仕組みの対象となる場合のみです。
在職老齢年金制度は、厚生年金に加入して給与を受け取っている人が一定以上の収入を得た場合に、老齢厚生年金の一部または全額が一時的に停止される仕組みです。年金と給与を同時に受け取っている人だけが対象です。
マンション経営の家賃収入は不動産所得に分類され、給与や賞与とは異なります。在職老齢年金制度の対象外であり、家賃収入があっても年金が減額されることはありません。
貯蓄よりも資産を増やしやすい
老後に備えて貯金をしても、低金利の時代ではお金はほとんど増えません。たとえば普通預金の金利が0.001%の場合、500万円を10年間預けても利息はわずか400円ほどです。物価が上がれば実質的な価値は目減りしてしまい、老後資金として十分とはいえないのが現状です。
一方、マンション経営は「家賃収入」と「売却益」の両方で資産を増やせる可能性があります。入居者からの家賃で安定した収入を得ながらローンを返済していけば、時間の経過とともに不動産は資産として残ります。立地条件などが良ければ、購入時より高い価格で将来売却できることも珍しくありません。
不動産投資は、少ない自己資金でも融資を活用して始められる点が貯蓄との大きな違いです。家賃収入を返済に充てられるため、自分の給与を使わずに資産を増やしていけます。
インフレ対策になる
物価が上がるインフレでは現金の価値が下がる一方で、不動産のような現物資産は価値を維持しやすい傾向があります。特に都市部のマンションは需要が高く、物価上昇とともに家賃も上がりやすいため、インフレに強い資産といえます。
年金はインフレが進んでも、すぐに支給額が増えるわけではありません。そのため、物価上昇によって生活費が増えると、実質的に使えるお金が減ってしまいます。マンション経営は物価上昇に合わせて家賃を見直せるため、生活費への負担を軽減しやすいです。
不動産は「現金よりもインフレに強い」資産として位置づけられています。預貯金では金利が低いため資産が増えにくいですが、マンション経営なら家賃収入を得ながら資産価値の上昇も期待できます。
不動産投資はインフレ対策になる3つの理由|関係性や注意点も解説!
相続時の負担を軽減できる
不動産の相続税評価額は時価の8割程度といわれています。さらに、賃貸物件の場合は決められた減額割合が適用されるため、結果として相続税の負担を抑えられる可能性があります。
不動産を所有している期間の家賃収入を、相続税などの支払いに充てられます。現金を相続するよりも、毎月の収入を得ながら資産を引き継ぐことができる点がメリットです。また、相続時の分割方法として、物件を売却して現金化したり賃貸を継続したりするなど選択肢を確保できます。
相続税評価や減額は物件の種類や状況で変わるため、税理士に相談して納税額や分割案まで含めて相談しておくと安心です。
マンション経営で年金対策する3つのデメリット

マンション経営は安定して家賃収入を得られる方法ですが、思わぬ負担が発生する場合があります。とくに初めて不動産投資を行う方は、税制の仕組みや制度に戸惑うことが多いです。ここでは、マンション経営を年金対策として行う際に注意したい3つのデメリットを解説します。
確定申告が必要である
マンション経営で家賃収入を得る場合、原則として確定申告が必要です。たとえば会社員の場合、マンション経営による不動産所得が年間20万円を超えると申告義務が発生します。家賃が月8万円で経費を差し引いた所得が月2万円あれば、年間で24万円となり申告の対象です。
もし申告を怠ると、無申告加算税や延滞税といったペナルティが課されることもあります。税務署から指摘を受けてから修正すると、無申告加算税や延滞税などの追徴課税が発生するおそれがあるため注意が必要です。
確定申告は手間がかかりますが、支出を見直して経営の健全化を図るチャンスでもあります。管理費やローン利息などを経費として正しく計上すれば、税負担を軽くできる可能性があります。早めに帳簿を整え、税理士に相談して正確な申告を行うことで、安心して長期的な運用を続けられます。
税負担が増加する
マンション経営で得た家賃収入は、不動産所得として扱われます。給与所得と同様に課税対象となり、所得税や住民税を支払う必要があります。たとえ老後の生活費を補うための収入であっても、税務上は事業収入として扱われる点に注意が必要です。
物件を所有しているだけでも、固定資産税や都市計画税といった税金が毎年発生します。物件の評価額や所在地によって税額が変わるため、購入前に想定しておくことが大切です。
将来、物件を売却して利益が出た場合は、譲渡所得税が課されます。長期に保有すると税率が軽減される制度があるため、税金を含めた運用計画を立てておくと安心です。マンション経営を長く続けるためには、収入だけでなく税金や支出を含めたトータルの資金計画を立てることが重要です。
家族の扶養から外れる
定年後にマンション経営を始めて家賃収入を得ると、扶養から外れる可能性があります。年金と家賃収入の合計が一定額を超えると、税法上の「扶養控除」の対象外となるためです。
たとえば、配偶者や子どもの扶養に入っている場合、年金と家賃収入の合計が180万円を超えると扶養から外れるケースがあります。扶養している家族側の所得控除が減り、世帯全体の税負担が増えるおそれがあります。
扶養の判定基準は、年金額や家賃収入の規模や加入している制度によって条件が変わるため、事前に確認しておくことが重要です。もし扶養から外れる見込みがある場合は、どの程度の税負担増が想定されるのかを試算しておくと安心です。
年金対策で経営するマンションの選び方
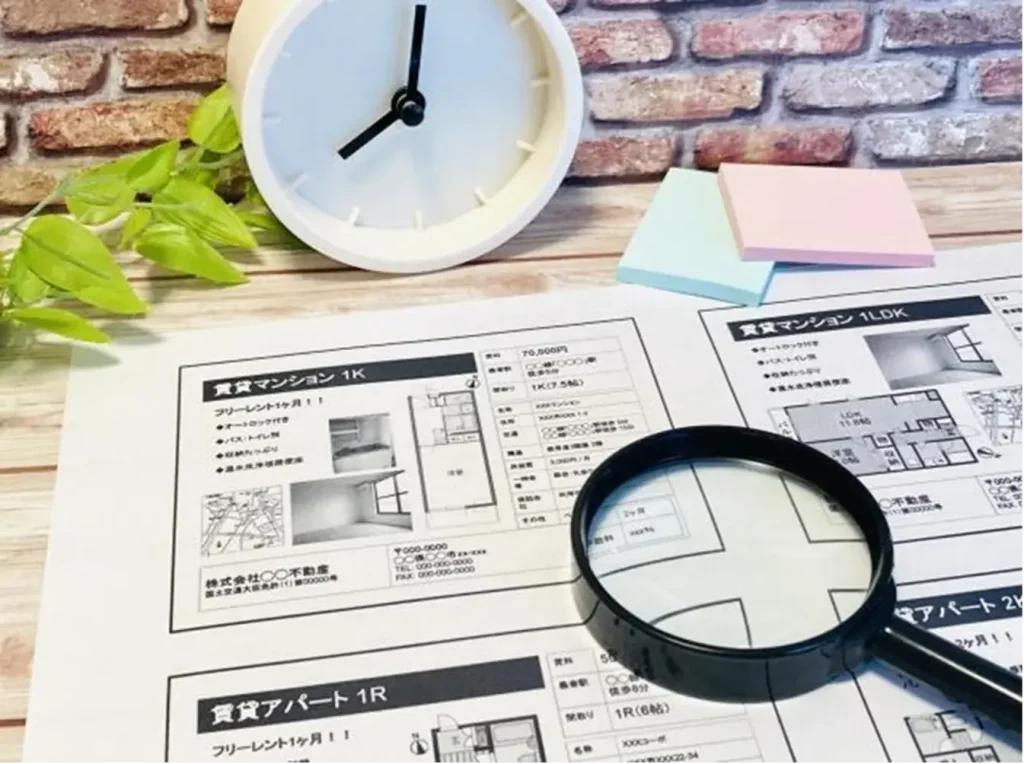
老後の生活費を支える収入源としてマンション経営を考えるなら、重要なことは物件選びです。どのようなマンションを選ぶかによって、将来の家賃収入の安定性や資産価値が大きく変わります。ここでは、マンション経営を年金対策として成功させるために押さえておきたい3つの物件選びのポイントを紹介します。
長期所有できる物件を選ぶ
年金を補う目的でマンション経営を始めるなら、長期的に家賃収入を得られる物件を選ぶことが重要です。老後の生活資金とする以上、短期的な利益よりも「長く保有し続けられるか」を基準に検討しましょう。
マンション経営では、家賃収入が定期的に得られる一方で、管理費や修繕費などの維持コストも発生します。築年数が経過すると、共用部や外壁の修繕が必要になるため、修繕費が計画的に積み立てられる管理体制の整った物件を選ぶと安心です。
また、長期的な需要を見込むために、立地選びも重要です。通勤や通学に便利な地域や、商業施設や病院が近いエリアは、安定した入居者が期待できます。人口が減りにくい都市部や交通の便が良い沿線は、空室リスクを抑えられる傾向があります。
自己資金が少なく始められる物件を選ぶ
年金を補うためのマンション経営では、最初は無理のない資金計画で始めることが大切です。初めから大規模な物件を購入するのではなく、ワンルームや小規模マンションなど、初期費用を抑えられる物件からスタートすると安心です。
マンション経営は、金融機関のローンを活用すれば、少ない自己資金でも始められます。たとえば、購入金額の1~2割を頭金として用意できれば残りは融資で対応できるケースも多く、手元資金を大きく減らさずにマンション経営を始められます。
ただし、空室や修繕などのリスクを考慮すると、毎月の返済や維持費を無理なく支払える計画を立てることが欠かせません。年金生活でも家計を圧迫しない範囲で返済できるよう、金利や返済期間のシミュレーションを事前に行っておきましょう。
需要のあるエリアの物件を選ぶ
せっかく物件を購入しても、空室が続けば家賃は得られずローンの返済や維持費だけが負担になります。年金対策として安定した収益を確保するためには、需要のあるエリアを選ぶことが重要です。
入居希望者が多いのは、交通アクセスが良く、生活利便性の高い地域です。たとえば、主要駅まで乗り換えが少ない沿線や、徒歩圏内にスーパーや病院などがそろうエリアは人気があります。大学やオフィス街が近い場所は、単身者や社会人など幅広い層からの需要も期待できます。
入居希望者が多い地域を選べば、毎月の家賃収入を安定して確保しやすくなるでしょう。結果として、年金と合わせて生活費を長期的に支えられます。
年収500万円のサラリーマンでも不動産投資は可能!必要な自己資金額と物件選びのコツを解説
毎年多くのお客様がトーシンパートナーズでマンション経営をスタートしています
月々1万円でローリスク&ロングリターンな資産運用

将来に対して漠然とした不安を抱えているものの「何から始めればいいのかわからない」と感じている方も多いのではないでしょうか。そんな方にこそ、ご紹介したいのがマンション経営という選択肢です。空室の発生や家賃の滞納といったリスクが気になるかもしれませんが、パートナーとなる管理会社を慎重に選べば、不安を抑えることは可能です。
月々1万円から無理なく始められるプランもあり、家計に大きな負担をかけずに将来に備えることができます。ご自身やご家族の将来の安心のために、ローリスク&ロングリターンな資産形成を検討してみてはいかがでしょうか?
Amazonギフト券
プレゼント限定キャンペーン
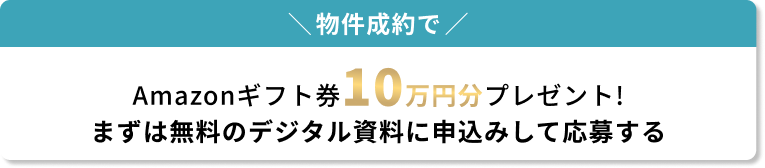
プレゼント適用条件はこちら
≪特典付与の条件≫
- ■キャンペーン名
- 不動産投資マンションご成約でAmazonギフトプレゼントキャンペーン
- ■キャンペーン概要
- トーシンパートナーズで不動産投資マンションをご成約いただいた方へ、もれなく10万分のAmazonギフトをプレゼント。
- ■キャンペーン対象期間
- 2025年11月5日~2026年2月28日
- ■キャンペーン対象条件
- 以下のすべての条件に該当する方
- 2026年2月28日までに資料請求、2026年3月31日までにご購入された方。
- 専用フォームからお申し込みいただいた方
※その他の方法でお申し込みの方は対象外です。 - キャンペーン期間中に初めてトーシンパートナーズで不動産投資マンションをご成約いただいた方。
- ■注意事項
- 本キャンペーンはトーシンパートナーズによる提供です。
- Amazonギフトのお受け取りは、お一人様1回限り10万円です。
- Amazonギフトは、物件購入のお申込みいただき、決済完了後の1か月以内にシリアルコードで送付予定となります。
- 本キャンペーンについてのお問い合わせはAmazonではお受けしておりません。
トーシンパートナーズマーケティング事務局【support@tohshin.co.jp】までお願いいたします。 - Amazon、Amazon.co.jpおよびそれらのロゴはAmazon.com,Inc.またはその関連会社の商標です。
まとめ:マンション経営で年金にプラスできる収入を今から準備しよう

年金だけでは老後の生活費が不足することが多いため、物価上昇や医療費の増加を考えると安定した追加収入の確保が欠かせません。マンション経営は「家賃収入」で年金を補える現実的な方法として注目されています。入居者がいれば毎月安定して家賃を得られ、長期的には不労所得として生活を支える心強い収入です。不動産はインフレにも強く、資産価値の維持や相続面でも有利に働く点が大きな魅力です。
確定申告や税金の支払いなど注意すべき点もありますが、正しい知識を身につけ計画的に取り組めば「年金だけでは生活費が足らない」という心配を払拭できます。
まずは、マンション経営の基本を理解することから始めましょう。限定スタートブックでは、初心者でもわかりやすく基礎知識や始め方を解説しています。また、おすすめの投資法がわかる公式LINEにも登録してみましょう。
よくある質問
Q1. マンション経営を年金対策にする場合、ローンは何歳までに完済すべきですか?
年金の受給が始まる65歳までには完済しておくのが理想的です。ローンが残っていると、退職して収入が減った後も返済が続き、家賃収入の多くが返済に充てられてしまいます。これでは、年金の補てんという本来の目的を果たせません。繰り上げ返済などを活用し、現役で収入があるうちにローンを完済する計画を立てることが重要です。そうすることで、年金生活に入ってから家賃収入を生活費やゆとりの資金として最大限に活用できます。
Q2. 年金対策でマンション経営を始める場合、団体信用生命保険(団信)のメリットは何ですか?
最大のメリットは、オーナー様に万が一のことがあった場合、ローンの残債が保険で完済されることです。これにより、ご家族に借金を残すことなく、家賃収入が得られるマンションを資産として遺すことができます。つまり、マンション経営が生命保険の代わりとしての役割も果たしてくれるのです。これは、公的年金だけでは不安が残る将来の備えとして、非常に大きな安心材料となります。
Q3. 年金対策としてマンション経営を始める際、物件選びで特に注意すべき点は何ですか?
長期的に安定した入居が見込める物件を選ぶことが最も重要です。具体的には、駅から近く、周辺にスーパーや病院などの生活利便施設が充実している物件が挙げられます。将来にわたって価値が下がりにくい、資産価値の高い物件を選ぶことで、空室リスクを抑え、安定した家賃収入を確保しやすくなります。目先の利回りだけでなく、20年、30年先を見据え、そのエリアの将来性や人口の推移なども考慮して、慎重に物件を選びましょう。